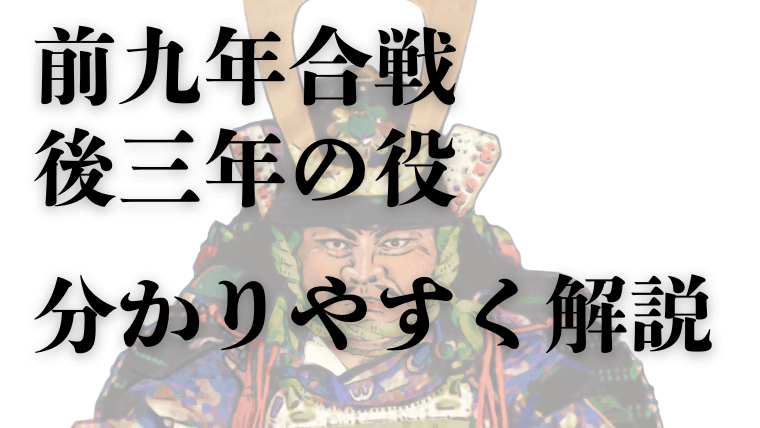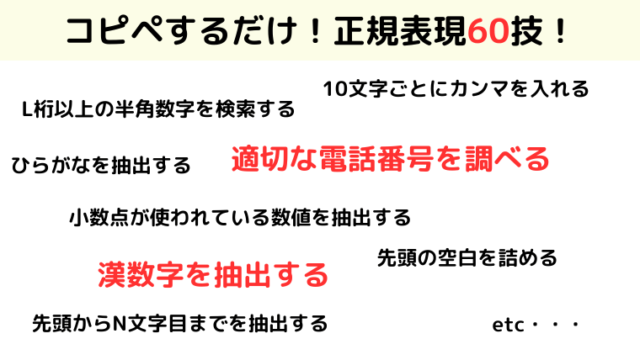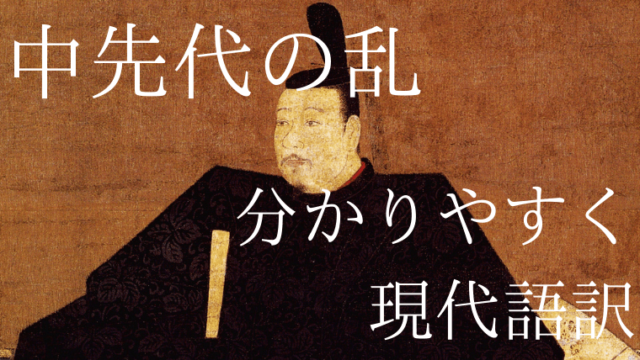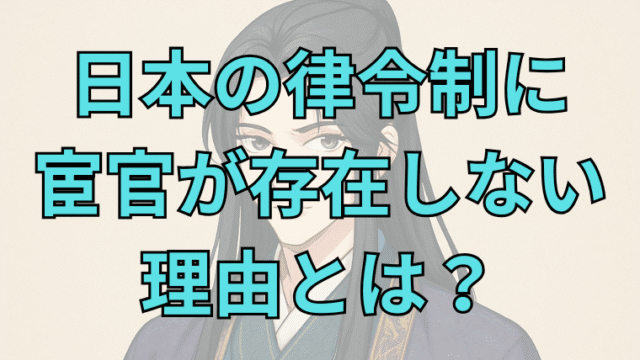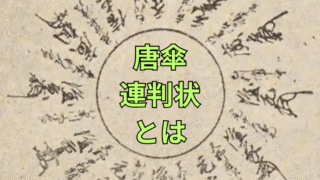前九年と後三年の違い
違いを表にまとめました。
| 前九年合戦 | 後三年の役 | |
| 別名 | 奥州十二年合戦 | 永保合戦 |
| 期間 | 1051~1062 | 1083~1087 |
| 年間 | 12年間 | 5年間 |
| 作品 | 『陸奥話記』 | 『奥州後三年記』 |
| 概要 | 源頼義 VS 安倍氏 | 源義家(頼義の子) VS 清原氏(安倍氏の後継)他 |
| 性格 | 物語性が強い | 史実性が強い |
「前九年合戦」は親世代の戦い、「後三年の役」は子世代の戦い、といった構図になっています。前九年が前に起きて、後三年が後に起きたのは分かりやすくて良いですね。作品名も『奥州後三年記』と後三年の役を連想させるものとなっています。
これら作品の特徴は、創作としての物語ではなく、朝廷の記録(国解)や武士の証言をもとに書かれた点です。文学性を有しておきながら、史料としての価値も有する貴重な古典籍になっています。特に『奥州後三年記』は年代記としての性格が強く、『陸奥話記』よりもその信憑性が高いと言われています(一部時系列に欠落がありますが)。
次は最も気になるであろう、戦いの年数の話です。「なぜ12年間なのに前九年?」「なぜ5年間なのに後三年?」なのかを見ていきましょう。
戦名の由来
「前九年」とか「後三年」とか紛らわしい書き方なのは、人々が戦の期間を誤認したためだと言われています。「後三年」から見ていきましょう。
戦の期間は以下の表の通りです。
| 前九年合戦 | 永承六年(1051)~康平五年(1062) |
|---|---|
| 後三年の役 | 永保三年(1083)~寛治三年(1087) |
「後三年」の由来
先に結論を述べると、
「後三年」の由来は、
合戦が京に伝わった年(1086)~源義家の陸奥守任期満了の年(1088)
が3年だったからです。
『後三年の役』は京から遠く離れた東北の地で起きたため、京でその合戦の状況をリアルタイムで把握することはできませんでした。数々の書簡の調査などから、東北地方豪族と源義家との戦闘が京に伝わったのは寛治二年(1086)であったと分かっており、これが2度目の東北内乱の開戦年と認識されました。そして、当時の人々は、源義家の陸奥守解任にあたる寛治四年(1088)が終戦だと判断したそうです。これが原因で3年間に及ぶ戦だと勘違い、この内乱の様子を描いた作品は、勘違いした作者によって『奥州後三年記』と命名されました。
合戦が京に伝わった年(1086)
~ 源義家の陸奥守任期満了の年(1088)
が内乱の期間であった、と人々が勘違いしたから
そして「前九年」も同様に人々の勘違いでこのように命名されました。
「前九年」の由来
こちらも先に結論から述べましょう。
「前九年」の由来は
(奥州十二年合戦)ー(後三年)= 九年
という誤った認識が原因です。
そもそも、1度目の東北合戦は「奥州十二年合戦」と呼ばれていました。しかし、「後三年の役」を題材にした作品が『奥州後三年記』という名で流布したことで人々の認識が変わります。どうしても『後』という字に引っ張られて、さらに『三年』なんて付いてるわけですから、人々は、
2度目(後)の合戦が「3年」だから、1度目(前)に起きた合戦は9年間か!
と勘違いし、『前九年』と認識してしまったようです。
(奥州十二年合戦)ー(後三年)= 九年
が内乱の期間であった、と人々が勘違いしたから
これが「前九年合戦」と「後三年の役」の年数の正体です。
内容
「前九年合戦」「後三年の役」の両合戦によって、源家は朝廷の威信に大きく貢献しました。この際、坂東(関東)から奥州にかけての武士を動員し、源家の門人として彼らを迎え入れたのですが、これが後の鎌倉幕府の基盤になったとも言われています。
『陸奥話記』には、源義家の武勇に魅了されて坂東の武士らがこぞって義家の門人となったという記述がある反面、『奥州後三年記』では、京から連れてきた郎党を中心に編隊されていたことが読み取れます。
冬の長期戦となった沼柵の戦いの際、兵は身の回りのものを削って、妻らに京への路銀となりそうなものを送るシーンがあり、後三年の役では京の武士が中心に描かれていることを考えると、坂東の武士の戦力を十分に発揮するのはまだ先であったとも言えましょう。源家隆盛のはじまりの戦いであったとも言えますね。
『陸奥話記』
『陸奥話記』は前九年合戦を題材にした物語で、主人公は源頼義です。地方豪族の安倍氏と源氏の抗争を描きました。
時系列は以下のようになっています。
- 1051年当時の陸奥守、藤原登任が横暴を働く安倍頼良を攻撃するも鬼切部の戦いで敗北。この敗戦によって源頼義が陸奥守兼鎮守府将軍に任命された。
- 1052年藤原彰子の病気快癒祈願として朝廷が大赦を行う。安倍頼良は罪が赦され、これを機に安倍頼時に改名。源頼義と和睦した。
- 1056年源頼義の兵が阿久利川で襲撃される阿久刀川事件が発生。安倍貞任がこの事件に関与したとされ、それに煽られた藤原経清などが謀反を起こす。
- 1057年抗争の中で安倍頼良が死亡。その後、安倍貞任を討とうと黄海の戦いが勃発するも、官軍敗北。
- 1062年官軍は、清原氏を懐柔し、勢力拡大を続ける安倍氏に決戦を挑み、小松柵の戦いが勃発。官軍が圧勝し、その後の衣川関の戦いなど一連の戦いで連戦連勝、最終決戦となった厨川柵の戦いでついに安倍氏を滅ぼす。
勃発の原因は、安倍頼良をはじめとする安倍氏の横暴を止めるためです。そこで源頼義が陸奥守と鎮守府将軍という大役を兼任することになりました。
安倍頼良と和睦したことによって一時安定した治国を行っていましたが、阿久刀川事件によって討伐へ意識が傾きます。本文を読むと分かるのですが、この事件の犯人や黒幕ははっきりしている訳ではなく、「人間関係のいざこざを考えるに、安倍貞任に違いない。」という道理が通ってそうな意見を正と捉えて話が進んでいます。
粛清に恐れをなした藤原経清の謀反などで本格的に前九年合戦が始まるのですが、この事件は討伐の名目を得るために、官軍側が自作自演した、とも言われています。源頼義には、「征夷」大将軍に任命されている以上、征討というかたちで結果を出す必要がありました。それが和睦によってできないままでいたため、このような行動に踏み切ったとも言われています。
作者は不詳ですが、源義家に関しては特にべた褒めした内容となっています。後三年の役で大手柄を立てたことを踏まえて書かれたと仮定しても、単に文学者が作品を書いたのではなく、源氏と繋がりのあった人物の手によるものだと考える方が自然でしょう。『奥州後三年記』では、両陣営の戦況を淡々と描いているのに対して、『陸奥話記』では圧倒的に官軍側のドラマが割合を占めています。特に小松柵の戦いでは、散位(官位を持たない者)の者の戦ぶりまで描いているほどで、一部の武士では現実としては嘘くさいようなストーリーが含まれています。
とはいえ、それだけ詳細にかかれたおかげで、陣形や懐柔作戦、城の攻略方法といった当時の戦の手法を垣間見ることができる史料とも評価されるようになりました。
『奥州後三年記』
『奥州後三年記』は後三年の役の発端から終戦までを描いた全3巻の物語です。作者不詳で、最後の一文には「誤った部分は識者の訂正を願う」とあるため、実際に出陣にあたった人物が書いてはいないようです。今回の主人公は、約10年前に勃発した前九年合戦の主人公源頼義の息子、源義家です。
この5年間で対戦カードが3度変わります。
- 前日譚:勃発のきっかけ吉彦秀武が源義家から恥辱を受け、恨みを抱く
- 第1戦:吉彦秀武討伐戦源義家・清原真衡VS藤原清衡・吉彦秀武・清原家衡
- 第2戦:清原家衡討伐戦源義家・藤原清衡VS清原家衡
- 第3戦:金沢柵籠城戦源義家・源義光・藤原清衡・吉彦秀武VS清原家衡・清原武衡
一貫して賊軍の清原家衡に対し、第1戦の賊軍であった藤原清衡、吉彦秀武は最終的には官軍側につきました。官軍の謀略や身内での内部分裂によって、討伐対象の人物はコロコロと変わりますが、基本的に賊軍は清原家になります。この火花は東北地方全体に広がったわけですが、その多くの豪族が日和見や寝返りを繰り返したようで、家衡・清衡はほとんどとばっちりに近い形で参戦、内乱となりました。
清原家衡をはじめとするこの清原家が奥州で猛威を振るったのは、前九年合戦の際に滅ぼされた安倍氏の後釜であったためですが、猛威を振るうというわりには温厚な性格で、平和に東北地方を治めていました。吉彦秀武に続き、清原真衡という人物がちょっとした過ちを犯したせいで一気に緊張状態が高まり、これが原因で身内問題が発生、鎮圧しようと官軍が横やりを入れてきたことによって後三年の役が勃発してしまいます。
元凶となった吉彦秀武の件ですが、これは、源義家が吉彦秀武の全力の宴会芸をガン無視したためです。前日譚にあたります。吉彦秀武は、前九年合戦でも戦い抜いた歴戦の武士であり、また東北地方屈指の地方豪族でしたが、そんな背景も気にせず源義家は彼を蔑ろにしました。この侮辱は個人に留まらず東北地方の権力者全員に対するものと判断した吉彦秀武は、東北地方で動員できる兵をかき集め、挙兵したわけです。
第2戦にあたる家衡討伐戦は、実は本文中では書かれていない内容になります。団結して官軍(源義家)に立ち向かった東北勢ですが、その中でも清原家が源義家から東北地方の統治権を与えられたことによって、その処遇を巡り対立。身内争いが始まりました。これが源義家の狙いだったとも思われます。当ブログでは、この欠落部分を要約で補完、以降の内容に辻褄が合うように追記しています。
第3戦にあたる金沢柵籠城戦では、かの有名な「雁の乱れに敵兵を知る」のもととなったシーンが描かれています。賊軍(東北勢)が敗北する結末なのですが、落城後の惨状(有力武士、女性)があまりにもきつく描かれているので、苦手な人は落城シーンだけ飛ばすのも良いと思います。
現代語訳
一覧から各作品各巻にジャンプできます。
『陸奥話記』
『奥州後三年記』
まとめ
九年と三年の由来は分かったでしょうか。あくまでも有力とされている説なので、将来研究が進んで邪説となる可能性も無きにしも非ず。ただ、筋は通っているので、俗説として扱うほど杜撰な論拠でも無いと思います。古文書研究を踏まえたうえでの結果となっているためです。
両作品は、単なる年代記とは一線を画した作品で、武士と地方豪族の実際の対立をリアルに描き出した作品となっており、特に戦後においては、源氏に対して論功行賞をしている記録から、当時の朝廷がいかに源氏の武力を高く評価していたか分かります。11世紀後半は、平家の凋落期で、源氏の勢力が伸びていたことの影響でもありますね。当時の政治構造も垣間見える史料とも言えましょう。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |