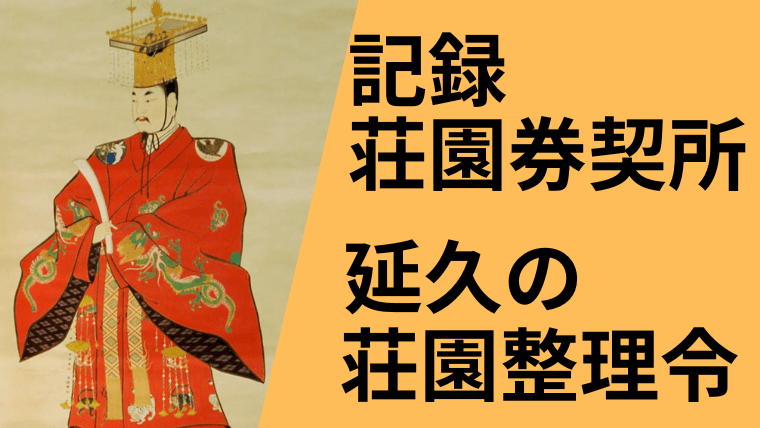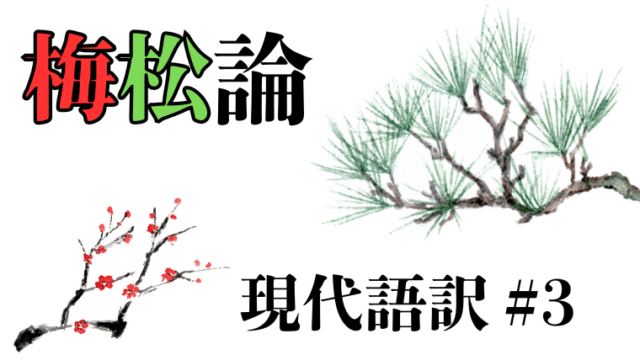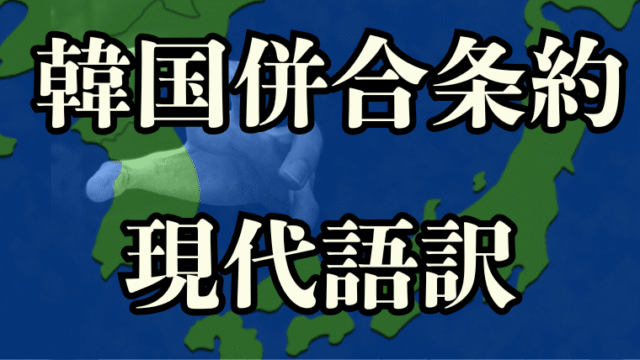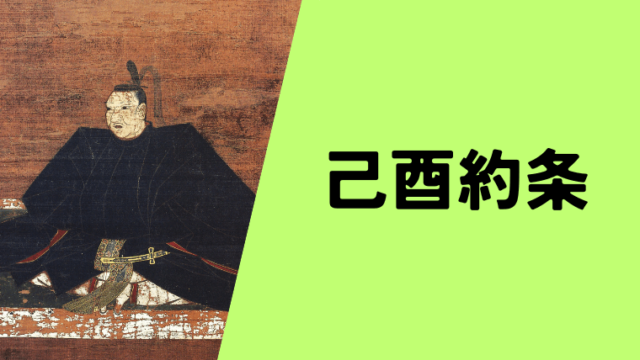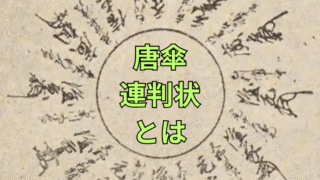プロフィール帳
解説
延久の荘園整理令と記録荘園券契所の関係
『延久の荘園整理令』と『記録荘園券契所』は後三条天皇の御代に起こった出来事で、両者には深すぎる関係があります。
それは、『延久の荘園整理令』という後三条天皇の勅令に基づいて設置されたのが『記録荘園券契所』ということです。年号はいずれも延久元年(1069)になります。
どちらが先に出されたか?と質問の答えは簡単ですね。前後関係が分かっていれば、『延久の荘園整理令』が先だとすぐ分かります。
さて、それぞれを詳しくみていきましょう。
延久の荘園整理令
時代背景
延久元年(1069)はまさしく藤原氏全盛期にあたります。史料『延久の荘園整理令』にもあるとおり、藤原氏の恩恵を得ようとした地方豪族や役人が不正に藤原氏に対して上納行為が流行しました。
この上納行為とは、平安時代末期にあたる「寄進地系荘園」のことを指します。荘園を権力者に寄進することを指すのですが、この手続きが無法地帯でした。違法に開発された荘園、勝手に公領の一部を私領と主張し奪取された荘園、口約束が多く領主が不明などといったカオスな国情で、これにより、本来朝廷に納められるはずの税収が減少したのみならず、国内の秩序が乱れました。長い歴史の観点からみれば、これが武士の誕生にもつながります。
ではなぜ「寄進地系荘園」が流行したのか。それは遠くない100年ほど前に誕生した「不輸・不入の権」が原因となっています。納税を免除される「不輸の権」と、税を徴収する役割を担う国司の、荘園への出入り制限した「不入の権」の存在によって荘園の管理体制が杜撰になったのです。
10世紀も藤原氏が隆盛していた時期で、時の地方豪族や荘園領主は政治権力のバックアップを狙って藤原氏への接近を試みました。その時に目を付けたのが荘園です。土地という不動産は、食料という生産力と人という労働力を集めることができる最強のプラットフォームです。交渉材料には最適でした。それに対して藤原氏のメリットは、領有する土地が多ければ多いほど権勢がさらに盛んになるということでした。荘園に従事する人は必ずその所有者と従属関係を結びます。荘園を増やせば増やすほど、権門を支える人口増加と生産力の増加が見込めたわけです。
こうして、荘園の存在をもとに、栄華を極めようとする藤原氏とそれにあやかりたい地方豪族の利が一致し、「寄進地系荘園」が流行したのです。
もとはといえば、荘園の管理体制が厳格になされていれば、このように荘園が寄進されることもなかったことはお分かりでしょう。
そこで出されたのが、このような不正荘園を一掃する『延久の荘園整理令』だったのです。具体的な施策として、『記録荘園券契所』が設置されました。
整理令が特殊である理由
『延久の荘園整理令』は非常に強気な施策でした。というのも、「寄進地系荘園」や「不輸・不入の権」の既得権益で美味しい思いをしてきた全盛期の藤原氏もとい地方豪族までもが調査の対象だったためです。かつてこれほどの権門勢力に対して牙をむいた天皇はいたでしょうか。ではなぜ後三条天皇はそれが可能だったのでしょうか?
なぜ可能だったのか?
なぜこのような勅令を出すことが可能だったのでしょうか。藤原氏に不利な施策を提起すれば、反発されるのは自明の理です。その答えは後三条天皇の出自に関係があります。
それは、後三条天皇が宇多天皇以来170年ぶりに藤原氏を外戚としない天皇だったからです。
要するに、後三条天皇は摂関家(藤原氏)の一族の娘を妻に迎えなかったということです。その分、藤原氏の影響を大きく受けず、むしろ自身の理想とする政治を志すことができました。
背景は省略しますが、政治戦略を誤った藤原氏は、後三条天皇の一連の施策によって、そのしっぺ返しを食らったのです。
記録荘園券契所
記録荘園券契所という機関名
延久元年(1069)に設置された令外官 (りようげのかん) の一つで、またの名を『記録所』ともいいます。一言で言い表せば、荘園を整理するための事務処理機関です。太政官庁の朝所に設置されました。
史料『延久の荘園整理令』では、『立券(荘園を証明する正式文書を受けること)があったか否か不明な、国務の妨げとなっている荘園は停止する。』とあります。
この「立券」というのは、荘園を証明する正式文書を受ける行為のことを指します。そして、この正式文書のことを「券契」というのです。
要するに、『記録荘園券契所』は
記録荘園券契所=荘園証明書(券契)を記録する所
ということなのです。
業務内容
さて、どのような事務手続きが行われていたかという話ですが、「立券があったか分からない荘園は停止する」ということですので、裏を返せば、券契を提出させていたことが分かります。
実際、地方官から券契を提出させ、それを「記録荘園券契所」の役人(寄人)が調査しました。
荘園停止の対象となったのは以下の条件です。
- そもそも証明書の受領(立券)が不明な荘園
- 寛徳二年(1045)以降、新立された荘園
目的
『記録荘園券契所』を設置した目的は何だったのか。目的は2つです。
- 藤原政権の財政圧迫
- 天皇政治の再興
既得権益を貪っていた藤原氏をはじめとする権門の基盤を脅かすことで、藤原氏の勢力を抑えようとする目的がありました。本来国家に納税されるはずの租やその他品々は、土地ごと藤原氏が領有しており、そのままこれが藤原氏隆盛の基盤となっていました。荘園を整理することによって、藤原氏の抑圧と国家の財政安定化を図ったのです。
また、数百年ぶりに藤原氏の外戚をもたない後三条天皇は天皇政治の再興を望んでいたと言われています。その証拠として、次の天皇、白河天皇は院政を開始しました。藤原氏の終焉を加速させた天皇ともいえましょう。
現代語訳
延久の荘園整理令(赤文字)
『百錬抄』巻第五
元年己酉二月十日。依当梁年。今年不可作内裏之山被定之。諸道勘中。
延久元年(1069)。二月十日。今年、内裏の山を作らず、合議によって定められた。あらゆる専門の役人の意見の上である。
二十三日。可停止寛徳以後新立庄園。縦雖彼年以往。立券不分明。於国務有妨者。同停止之由宣下。
二月十三日。後三条天皇より宣旨が下された。『寛徳二年(1045)以後、新しく成立した荘園を停止する。たとえ寛徳二年以前に成立した荘園であっても、立券(荘園を証明する正式文書の授受)があったか否か不明な、国務の妨げとなっている荘園は停止する。』と。
閏二月十一日。始置記録所庄園券契所。定寄人等。[於官朝所始行之。]
閏二月十一日。記録荘園券契所を設置する。その職員等を定めた(「上卿ー弁ー寄人」で構成)。初めは朝廷の管轄より行われる。
三月十五日。石情水御幸之間。於路頭御輿●折。[六月五日依此事奉幣二十一社。]
三月十五日。後三条天皇が石清水八幡宮に御幸された。路頭において、神輿が折れた。なお、この石清水八幡宮を始めとして、六月五日に二十一社に幣を奉納なさった。
四月二十八日。立第一親王貞仁(白河)為皇太子。
四月二十八日。第一親王、貞仁王が立太子された(次の天皇、白河天皇のこと)。
五月二十九日。始行平等院一切経會。
五月二十九日。平等院で一切経会が行われた。
六月二十一日。自大宮院遷御高陽院。件院者帝旧居也。今加造舎屋有御幸也。
六月二十一日。大宮院から高陽院へ遷都した。院は天皇のかつての居宅で、今、屋敷を増築して、御幸された。
七月二十二日。令御厨子所預。始令供精進御菜。
七月二十二日。御厨子を管理するよう命があり、御菜物を精進した。
記録荘園券契所を設置した理由
『愚管抄』巻第四
延久ノ記録所トテハジメテヲカレタリケルハ。諸国七道ノ所領ノ宣旨官符モナクテ公田ヲカスムル事。一天四海ノ巨害ナリトキコシメシツメテアリケルハ。スナハチ宇治殿ノ時一ノ所ノ所領トノミ云テ。庄園諸国ニミチテ受領ノツトメタヘガタシナド云フ。キコシメシモチタリタケリルニコソ。サテ宣旨ヲ下サレテ。諸人領知ノ庄園ノ文書ヲメサレケルニ。宇治殿ヘ仰ラレタリケル御返事ニ。皆サ心得ラレタリケルニヤ。五十余年君ノ御ウシロミヲツカウマツリテ候シ間。所領モチテ候者ノ強縁ニセンナンド思ヒツツヨセタビ候ヒシカバ。サニコソナンド申タルバカリニテマカリスギ候キ。ナンデウ文書カハ候ベキ。タゞソレガシガ領ト申候ハン所ノ。シカルベカラズタシカナラズ聞シメサレ候ハンヲバ。イサゝカノ御ハゞカリ候ベキ事ニモ候ハズ。カヤウノ事ハカクコソ申サタスベキ身ニテ候ヘバ。カズヲツクシテタヲサレ候ベキナリト。サハヤカニ申サレタリケレバ。アダニ御支度相違ノ事ニテ。ムコニ御案アリテ。別ニ宣旨ヲ下サレテ。コノ記録所ヘ文書ドモメスコトニハ。前大相国ノ領ヲバノゾクト云宣下アリテ中ゝゝツヤゝゝト御沙汰ナカリケリ。コノ御沙汰ヲバイミジキ事カナトコソ世ノ中ニ申ケレ。
延久年間に記録荘園券契所を設置した理由は、諸国七道、つまり日本全国の公領が宣旨や官符がなくても横領されているという現状があったためである。後三条天皇が、これが日本において甚大な害となっているとお考えになったためであろう。
宇治殿(藤原頼通)が実権を握っていた頃、後三条天皇は『全国の荘園が、摂関家の所領しかないような状態ではないか。これでは、受領が国務を果たすことができない。』と仰ったという。こうお思いになっていたからこそ記録荘園券契所を設置したのであろう。
さて、天皇はまたこう宣旨を下された。『諸国の荘園領主は荘園を所有しているという旨の公的文書を提出せよ。』と。
これに宇治殿が奏上する。
「皆がそのようなものは無いと認識していることでしょう。五十年あまり天皇の後見人として勤めて参りましたが、この間に、所領を持つ者から、何度も荘園の寄進を受けました。私と強引にでも繋がりを持とうと思ったのでしょう。私は、「そうであるか。」とだけ言って受け取ってきました。どうして公的文書がありましょうか。「これは私の所領だ。」と言えば、それが正しいのです。所領であることは正しいのに、公的文書がないから確かではありません。天皇が『そうであってはならない。』『不明である。』と仰っていたのを耳にしましたので、ほんの僅か申し上げるのに憚りがありました。しかし、このようなことは申し上げておくべき身であると思いました。総体、国内は述べた通りの現状ですので、全て計画を断念するべきであると申し上げます。」
そうはっきりと答えた。
これによって天皇の計らいは全て無駄となってしまった。長く思案なさった天皇は別に宣旨を下された。『記録荘園券契所へ公的文書を提出する事に関して。前太政大臣、藤原頼通の所領の荘園については、公的文書の提出を無しとする。』と。せっかく厳密な調査のために設置したのに、かえってうやむやとなってしまった。
結果どうなったのか
史料では最終的に施策を断念したとありますが、全体的には成功といってよいと思います。
荘園を整理しただけあって、不明瞭であった公領と私領が明確に分断されることとなりました。その公領に関しては、新たな管理体制として、郡・郷・保という行政区画が誕生、一定の税収を得ることの成功したのです。適用範囲は公領にのみという部分に注意が必要です。かなり複雑な組織再編になりますので、これに関してはまた別の記事で解説しようと思います。
ここでは、荘園整理の結果として、「郡・郷・保」が誕生したと覚えておけばよいです。
また、政界の話をすれば、基盤を圧迫された藤原氏は全盛期ほどの権勢を振るうことが難しくなりました。後三条天皇の次の天皇である白河天皇が院政を始めたことを例に、時勢が天皇政治へと傾きはじめ、外戚としての影響力の衰えがより顕著になったのです。
以上、後三条天皇の見事な善政でした。