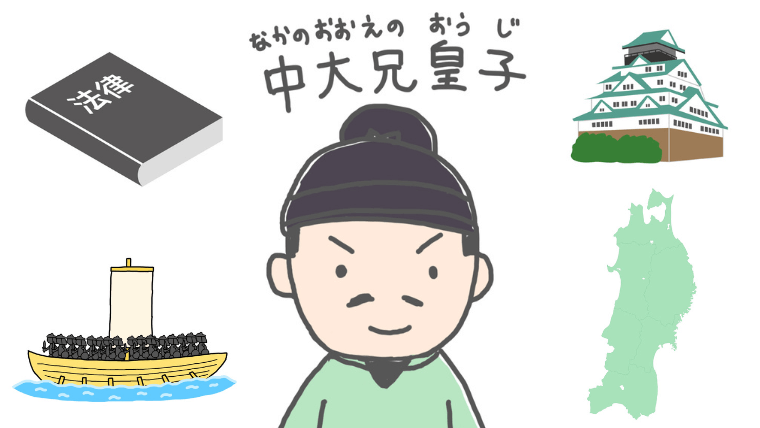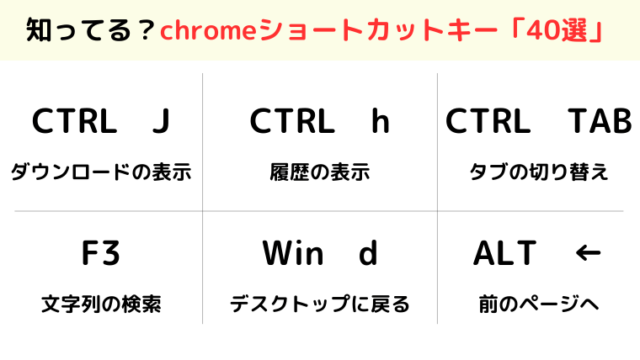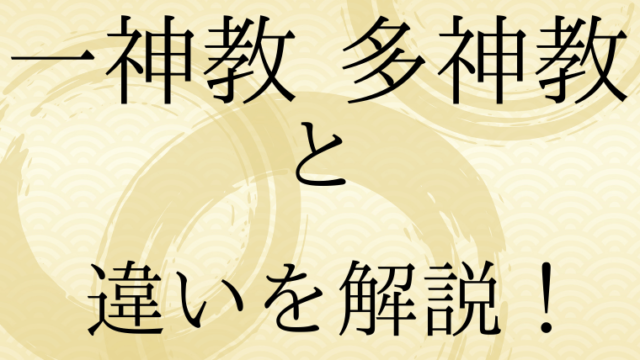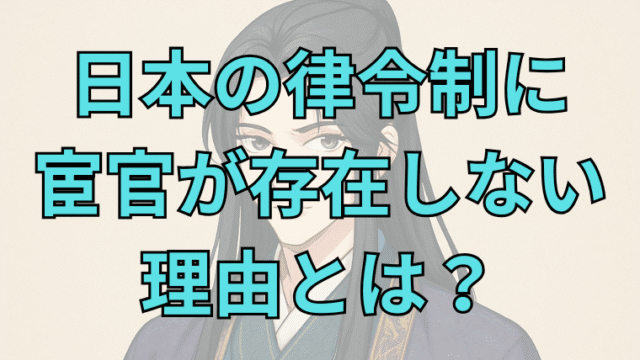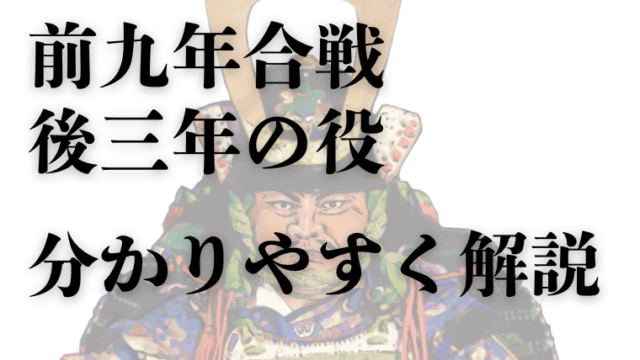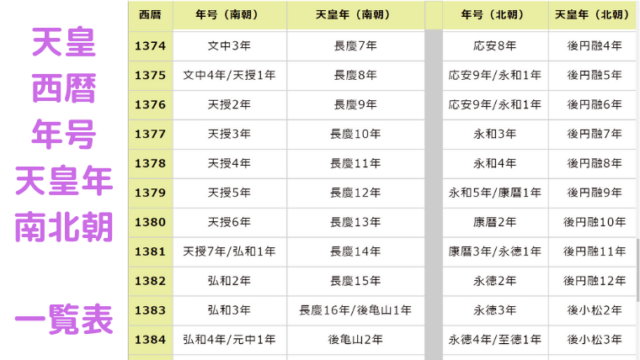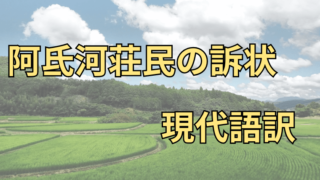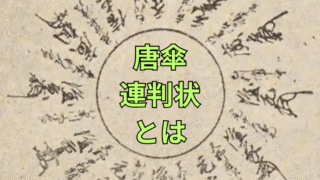小学校の教科書にも登場する中大兄皇子(天智天皇)。大化の改新の功労者として名高い存在ですが、当然、政権を握ってから古代日本の在り方を決定づける施策や、歴史的大事件にも関与するなど、激動の時代を作った人物でもあります。
そんな中大兄皇子(天智天皇)の功績を分かりやすく解説しました。
中大兄皇子(天智天皇)の功績
中大兄皇子は天智天皇として天皇に即位する前も様々な功績を残した人物です。主な功績を年表にしました。
- 645(大化の改新)孝徳天皇期。中臣鎌足らと共に蘇我氏を滅ぼした中大兄皇子は、日本の中央集権化を進める。『改新の詔』を主導した。
- 647・648(東北進出)孝徳天皇期。中央政府は支配領域の拡大に努めた。現新潟県に、647年にはぬたり柵を、648年には磐舟柵を築いた。
- 663(白村江の戦い)中大兄皇子称制期。百済再興に協力し、唐・新羅連合軍と戦うも惨敗。
- 664(水城造営)中大兄皇子称制期。現在の福岡県に土塁を築く。半島の技術が多く用いられており、亡命してきたの技術提供と考えられる。
- 667(近江大津宮遷都)中大兄皇子称制期。飛鳥から近江大津宮に遷都。遷都後、天智天皇として即位。
- 668(近江令制定)天智天皇期。のちの大宝律令の基盤となる『近江令』を制定した。
- 670(庚午年籍作成)天智天皇期。全国的な戸籍制度を導入。
- 672(壬申の乱)天皇空位。天智天皇が671年に崩御。発生した後継者争いとして壬申の乱が672年に勃発した。
ひとつずつ見ていきましょう。
645年:大化の改新
なぜ乙巳の変を起こしたのか
大化の改新は、蘇我氏を滅ぼした乙巳の変という政変後に進められた改革です。乙巳の変では、時の権力者蘇我氏を、天智天皇や中臣鎌足らが滅ぼしました。
原因は蘇我氏がある禁忌を犯したためです。それは、643年、蘇我入鹿が、聖徳太子の一族を蘇我氏が滅ぼしたこと(643年丁未の乱)。蘇我氏は、自身の方針に従わない権力者を抹殺しながら、皇族をバックに付けて傀儡として操ることで、自身の勢力を伸ばしていましたが、この時、皇族に留まっていた行動を、天皇家まで広げてきたのでした。
丁未の乱は聖徳太子の生涯を描いた『上宮聖徳法王帝説』にも記載されています。

これに危機感を募らせた中大兄皇子(のちの天智天皇)は中臣鎌足らと協力して蘇我氏を滅ぼすことに成功。これが乙巳の変です。
そして天皇位に座した中大兄皇子は、『改新の詔』を発布、次々と古代日本の基盤となる施策を打ち立てていったのです。
改新の詔
大化の改新の政策は主に4つです。
| 第1条 | 公地公民制 |
|---|---|
| 第2条 | 地方行政、軍事整備、交通の整備 |
| 第3条 | 班田収授法 |
| 第4条 | 税制 |
大化の改新は中央集権化(律令国家)への第一歩でした。蘇我氏になびいていた皇族、豪族を解体し、それらが所有していた人と土地という財産を国有にしたのです。それがこの4条に顕著にあらわれています。
詳しくはこちらで解説していますので、ご覧ください。

647年・648年:東北進出
647年に渟足(ぬたり)柵を、648年には磐舟柵を現在の新潟県に築きました。斉明天皇の時代には、阿倍比羅夫が派遣されています。
663年:白村江の戦い
超有名な歴史的事件ですね。663年に白村江の戦いが起きました。
ことの発端は百済滅亡。660年に唐・新羅連合軍によって百済が滅ぼされます。この百済の生き残りが、百済再興を目的として中央政府に救援を願い出ました。
そこで時の天皇、斉明天皇が直接九州に赴きますが、高齢ということもあり、筑紫国で崩御します。その後すぐに天皇即位というわけにもいかず、中大兄皇子が天皇代理といったかたちで兵・民衆を指導しました。この天皇代理を称制といいます。
臨時で天皇代理となること
そして白村江の戦いが勃発します。海戦で唐・新羅連合軍と激突し、統率のとれた大陸の軍隊に惨敗しました。
664年:水城造営
強大な軍事力を誇る唐・新羅連合軍に喧嘩を売ったようなものですから、当然、日本列島まで攻めてくる可能性は十分ありました。
そこで中大兄皇子は九州の政治的要所、大宰府周辺に防衛施設を建設します。水城や大野城、基肄城などを造営、そして防人を配置しました。
667年:近江大津宮遷都
飛鳥時代という名だけあって飛鳥宮に都が置かれていましたが、これを近江大津宮に遷都します。場所は名のとおり近江。現在の滋賀県周辺になります。
668年:近江令制定
近江大津宮で天智天皇は『近江令』を発布します。しかし、その法典が現存していないため、その実態は不明瞭です。
その後701年『大宝律令』を考えるに、もし『近江令』が存在していたら以下のような内容になるでしょう。
- 中央集権化への法整備、または強化
- 戸籍に関する制度
- 税制の細分化
もともと中央集権化を目指して大化の改新は行われたため、それを抜きには考えられません。また、戸籍に関する整備は、次に説明する庚午年籍の作成が関係していると思われます。
最後の税制の細分化は、大宝律令が税制に関して詳しく記されているため、段階的に制度を整えていったのではないかと思われます。
670年:庚午年籍作成
庚午年籍は日本で最初に作成された全国的な戸籍です。しかし『近江令』と同じく現存していません。
庚午年籍を作成した理由は、中央集権化を図るため、並びに、白村江の戦いに備えて兵力を確保する狙いもあったと思われます。
672年:壬申の乱
671年に天智天皇が崩御しました。天智天皇は生前、弟の大海人皇子に対して
「天皇になりたいか。」
とその意思確認を行っています。この際、大海人皇子は
「なりたくない。」
と答え、吉野に隠棲しました。これがきっかけで、息子の大友皇子に天皇位を継承することにしましたが、いざ天智天皇が崩御すると大海人皇子は態度を一変、大友皇子に攻撃をしかけ、大規模な内輪揉めが始めました。
兄の息子が相手だったので、親である天智天皇が存命の際は、荒波をたてないようにしていたのではないかと言われています。
まとめ
大化の改新にはじまり、まだ見ぬ制度を整えたり、外国勢力と交戦したり、壬申の乱の原因を残したりと、激動の時代を最前線で駆けていた人物。
壬申の乱も全部が全部悪いというわけではなく、この乱の結果、皇親政治の確立が進みました。歴史はどこかで繋がっています。それを伝えていくのも歴オタの使命だと思っています。
以上、中大兄皇子(天智天皇)の功績を時系列で説明でした!
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |