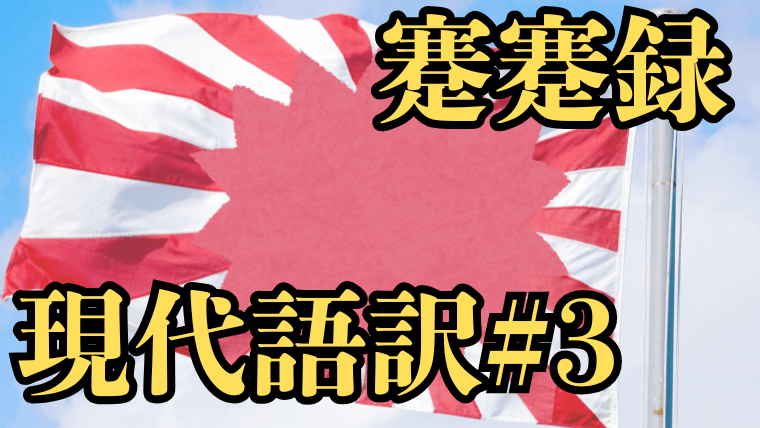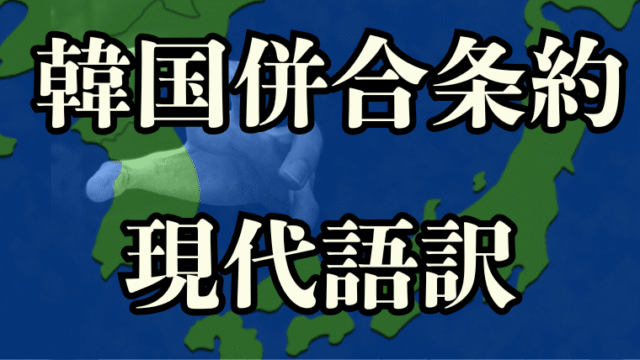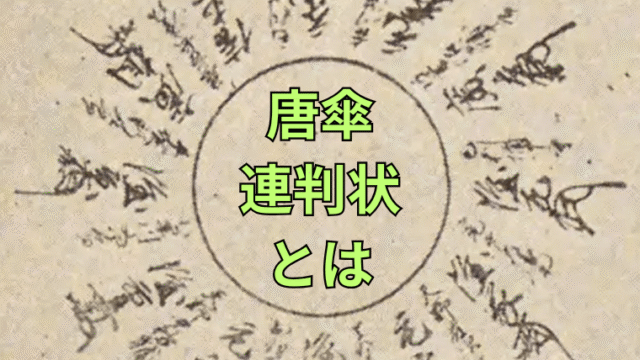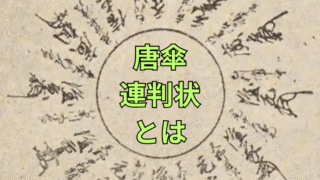現代語訳
第三章:大島特命全権公使の帰任及其就任後に於ける朝鮮の形勢
我が国の政府は、外交上においては常に受動的な立場を取ろうとする一方で、然るべき事態が生じた日には一旦受動的な立場を辞め、軍事上における全ての先手を取ろうと考えていた。そのため、清国が軍隊を朝鮮に派遣することが明確になった今、清国から天津条約に基づいた正式な通知が届くのを待つのは、先手を取り損ねる可能性もあって、非常に難しい状況であった。
このような我が国の状況に反して、清国の軍隊を移動させる自由度は我が国よりも高かった。単に仁川までの距離だけを言えば、清国の場合は山海関や大沽から高速蒸気船を使い直航すればわずか12~13時間で到着できるのに対して、我が国の場合は広島県の宇品港から約40時間を要する。
ともかく、当時の朝鮮の情勢は、大島浩特命全権公使の帰任を一日も遅らせることができないほど緊迫していたため、私は清国政府から天津条約に基づいた正式な出兵の通知を受ける2日前、すなわち6月5日に大島公使を軍艦「八重山」に乗せ、横須賀から出発させた。今回「八重山」には、新たに100名近い海兵が増員されており、また、幸いにも先に中国や南洋を巡視していた数隻の軍艦が数日前に釜山港まで帰航していたため、私は海軍大臣と協議して、それらの軍艦の一部を急ぎ仁川に回航させて釜山港の守備に当たらせるようにした。
同時に、大島公使が仁川に到着して後、京城に向かう必要が発生した場合には、大島公使の要請に応じて「八重山」に乗船している海兵に加え、他の軍艦から若干の海兵を追加して大島公使の移動に対応するようにも求めた。つまり、少なくとも300から400名の海兵は常に大島公使に随伴することを意味する。彼の赴任が容易になるよう手配を行ったわけである。これは、大島公使が朝鮮に到着する瞬間にすでに現地に清国兵が駐在していた場合、日本が同等の力を保つことを清国に示すことを意図したが故の手配であった。
しかしながら、我が政府は、国家の名誉が損なわれる事態に至らない限り、あくまでも平和的な手段を尽くして事態の収拾を図る方針を立てていたため、私は大島公使が東京を出発する際に、極めて詳細な訓令を数件与えた。その中で、
「朝鮮の状況に関して、今後政府は相当の軍隊を派遣する可能性がある。しかし、極めてやむを得ない場合に至るまでは、平和的手段によって事態を収束させることを第一義とせよ。」
との方針を伝えた。とはいえ、なにぶん当時の情勢がすでに切迫していたため、この訓令には
「もし状況が急変して、本国政府からの訓令を待つ余裕がない場合には、臨機応変に、大島公使が適切と判断する対応を取ることができる。」
との一項も加えておいた。これら訓令は、あたかも矛盾する二つの主義が含まれているようにも見えなくもないが、見ての通り緊張した日清情勢の中である。国外に派遣される公使に特別に権限を与えるのは、やむを得ないことであった。大島公使は6月9日に仁川に到着してすぐに各艦から集めた300名あまりの海兵を率いて京城に赴任、その後、第5師団から派遣された一戸兵衛(いちのへひょうえ)少佐が率いる一大隊の陸兵も京城に到着した。また、これに加えて日本政府が予定していた混成旅団の全員が順次朝鮮に派遣されることとなった。
ところが、大島公使が京城に赴任するも、清国軍隊はすでに朝鮮国内に到着していた。忠清道の牙山に駐留していた。また、朝鮮の官軍も最近やや士気を回復したようで、これにより東学党は大きく勢いを失い、ほとんど進軍が止まった状態であった。京城や仁川なども平穏を保っていた。
このような京城であったため、清国と朝鮮の両政府は、大島公使が大規模な兵を率いて帰任したことに驚き、さまざまな口実を設けて大島公使一団の武装状態での入京を拒もうとした。しかし、日清間においては、すでに天津条約に基づき互いに出兵通知を送り合ってたし、また日韓間においては、日本は済物浦条約第五条に基づき朝鮮に軍隊を派遣する条約上の権利を持っていたため、清朝両国は日本に対して表向きには何らの抗議もできなかったのである。これはあくまでも表向きな側面の話である。実際は、清朝両国は様々な陰謀を駆使して、日本軍が一日でも早く朝鮮から撤退するよう画策していた。
その真意は定かではないが、清国政府は袁世凱に訓令して、大島公使に対して日清両国の相互撤退を内々に提案させていた。一方で、朝鮮に駐在している外国の官吏や商人たちの様子を観察すると、彼らの表向きな意図はともかく、内心では朝鮮は清国の属邦であると認識しており、今回の清国の出兵も朝鮮国王の要請に基づいていたものだと信じていたようである。
また、彼らの中に日韓間に済物浦条約が存在することを知っている者は少なく、もし日清両国が戦争に至った場合、最初の一、二戦の結果はともかく、最終的な勝利は清国に帰すると予想していたようであった。日本軍は現地においてよくよく規律と節制を守り、少しも犯罪を犯さないという素晴らしい振る舞いを示した。このことは頗る外国人らに驚きと賞賛をもたらした。
とはいえ、どれだけ平和的に行動してもやはり軍人は軍人であり、京城と仁川の間に約7,000名以上の日本軍が駐留しているという事実は、彼ら外国人の目に非常に奇妙に映り、そして不安を感じさせるものであった。彼らは京城と仁川の間で多数の日本軍が活動しているのを日常的に目にしていたが、牙山に駐留している清国軍の動きについては全く目にも耳にも入ってこなかった。全体的に言えば、彼ら外国人は、日本政府の出兵の名目や真意を問わず、
「日本は平穏な今の状態に波を立て、状況に応じて朝鮮を侵略しようとしているのではないか。」
と勝手に妄想していたため、彼らは日本よりもむしろ清国に対して多くの同情を示していた。朝鮮に駐在する欧米の外交官や領事官らは、それぞれの推測を自国政府に報告していたに違いない。この日清事件の初段階が、諸欧米列強国の感情を揺さぶったのは疑いようがない。大島公使は帰任後すぐに現地の状況を観察。彼の所感に誤りはなかった。
京城に入ると、出発前に予想していた状況とは異なり、朝鮮国内は意外にも平穏で、清国の軍隊も牙山に駐留するだけで、内地への進軍には至っていなかった。また、第三者である外国人の様子は先述の通りであった。大島公使は頻繁に日本政府に電報を送り、
「あまりに多くの軍隊を朝鮮に派遣することは外交上好ましくない。というのも、朝鮮政府や朝鮮国民が不安を感じることに加えて、第三者である外国人が、根拠のない疑念を抱く可能性があるためだ。」
と勧告した。しかし、日本国内の状況はすでに途中で計画を変更できないほどの「騎虎の勢い」となっていたため、予定していた兵数を変更することが不可能となっていた。加えて、従来の清国政府の外交方針を考えてみるに、今後どのような策略や詐術を駆使して日本を欺いてくるかも予測できなかった。また、最近天津や北京から届いた電報によれば、清国はさらに多くの軍隊を朝鮮に送るべく出兵の準備を急いでいるという。
こうした一面から、大島公使の勧告が適切と思われたものの、他方では当初政府が予定していた混成旅団を速やかに朝鮮へ派遣しておくことが最善だと判断された。いつどのような不測の事態が起こるか分からないため、もし危機一髪の事態が発生すれば、その勝敗は完全に兵力の優劣に左右されると考えられたためである。
私は大島公使に対して、たとえ外交上の揉め事を多少生んでしまっても、大島少将が率いる本隊(混成旅団)を全て京城に駐留させて、なおかつ朝鮮政府に対して
「東学党の乱の鎮圧には、日本軍の手を借りるのが得策である。」
と説得し、我が軍を貸し出す形で援助するように指示した。以上略述したように、我が政府の計画は、外交面では受け身の立場をとりつつも、軍事面では常に主導権を握ろうとするものであった。このような緊迫した状況下だからこそ、外交と軍事が緊密に連携できるために、各担当者は非常な苦労を重ねたわけである。今でも当時の緊張感を思い返すと、身が引き締まる。
現在、日清両国の軍隊がともに朝鮮国内に駐留しているが、両国の駐屯地に距離があるため、即座に衝突が起きる危険性はないように見えるし、また東学党も表向きは鎮静化された様子である。
しかし、日清両国の軍隊はなおも互いに牽制し合っており、また各々不安と希望とを抱きながら対峙していたため、日清両国が和解して共に朝鮮国内から軍を撤退させるのはほとんど望めない状況であった。かといって、切羽詰まった理由や表向きの口実もないこの状態で交戦するには無理がある。したがって、国内事情と外交事情との両方に対処するためには、何らかの外交戦略を用いて事態を転換する道を探すほか手段はなかった。
| 前に戻る << | 次の記事へ >> |