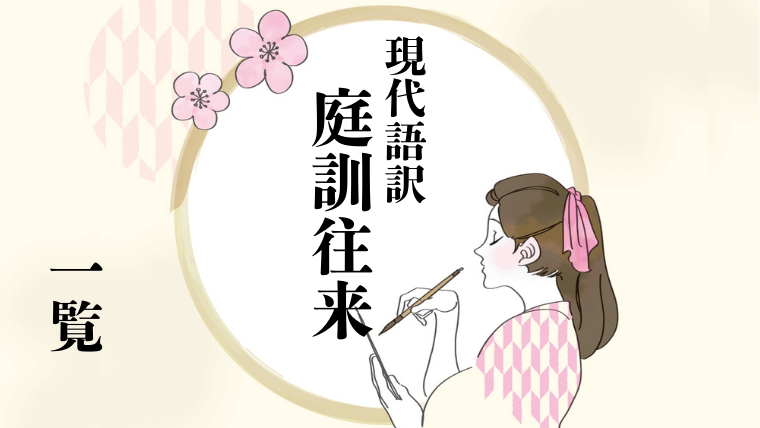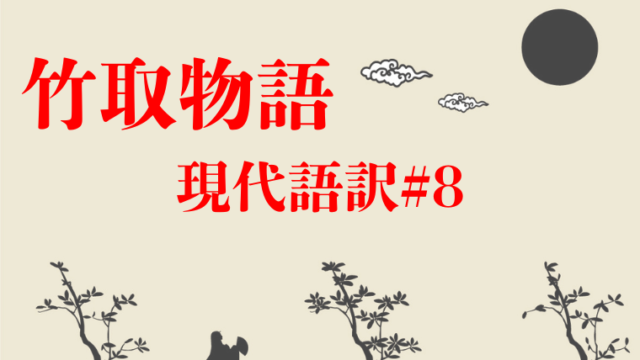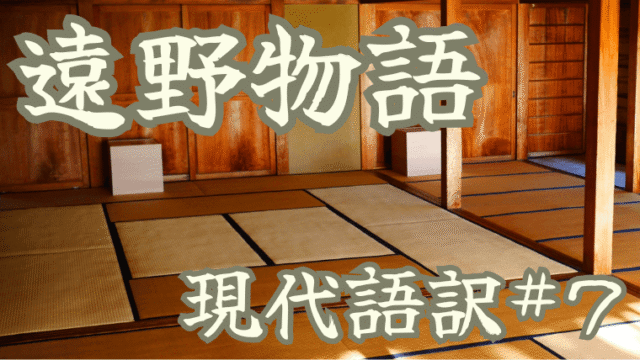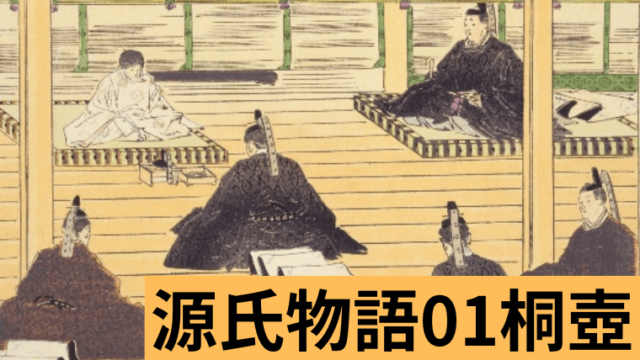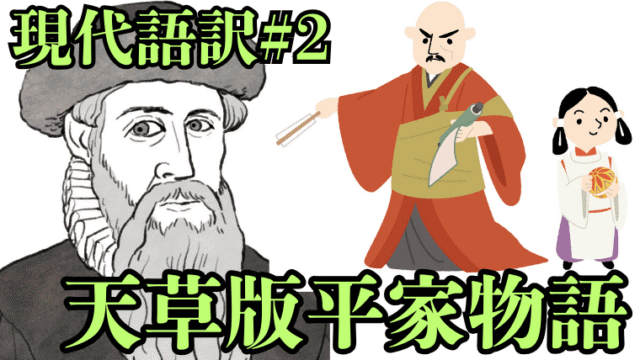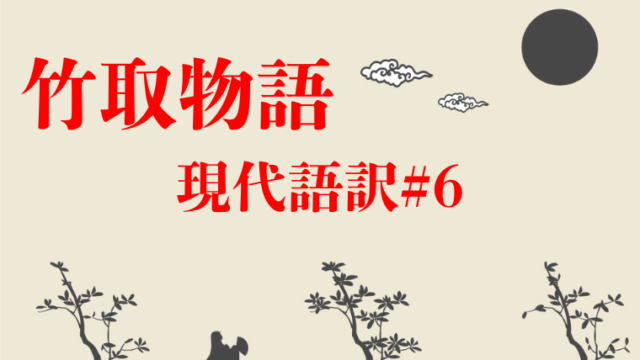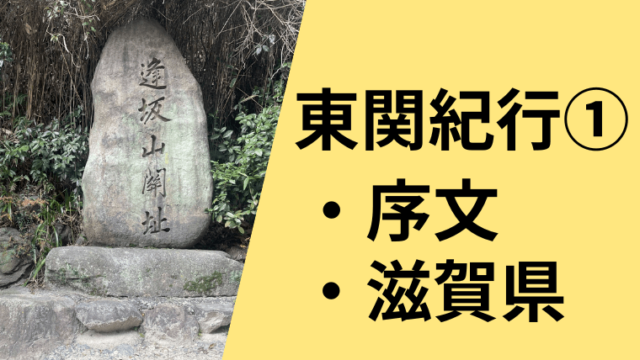スポンサーリンク
こんにちは、とらちゃです。室町時代には魅力的な文学作品が多くウハウハしています。
さて、今回は『庭訓往来』の現代語訳と解説を行います。高校日本史では名前だけ紹介されてサッと流されることが多いこの作品。その中身はいったい何なのでしょうか?
この記事から分かること
- 『庭訓往来』とは?
- 『庭訓往来』の内容(現代語訳)
スポンサーリンク
庭訓往来の意味
『庭訓往来』という言葉を聞いて何のことかピンとこない人が多いと思います。単語を分解してみましょう。
- 庭訓:家庭内で教えられる教訓のこと
- 往来:「往来物」のこと
「往来物」とは、往来するモノ、つまり手紙を指します。「家庭内で教えられる手紙」ということはつまり、教えるに相応しい内容が書いてある、ということです。
実際、『庭訓往来』では、文法・表現・物の名称・年中行事・算術・筆跡が記された往来物が収録されています。
庭訓往来とは?
教育に有益な情報が多く記載されている手紙のことで、中世において教科書として用いられた。
他には、『実語教』という作品が、教科書に用いられていました。『実語教』はこちらで現代語訳しています。
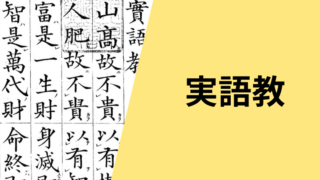
実語教【現代語訳】室町時代の教科書には何が書かれていた? プロフィール帳 『実語教』
時代:室町
作者:不詳
概要:中世の教科書のひとつ。学問を学び、知恵を身につけること...
庭訓往来の概要
全部で25通あります。基本的に2通で1セットです。つまり約12セット。月ごとの往来物を教科書として採用したわけですね。
青文字になっている部分からリンクで飛べます。
| 1セット | 01:正月五日状往信 02:正月六日状返信 |
|---|---|
| 2セット | 03:二月二十三日状往信 04:二月二十三日状返信 |
| 3セット | 05:三月七日状往信 06:三月十三日状返信 |
| 4セット | 07:四月五日状往信 08:四月十一日状返信 |
| 5セット | 09:五月九日状往信 10:五月日状返信 |
| 6セット | 11:六月七日状往信 12:六月十一日状返信 |
| 7セット | 13:七月五日状往信 14:七月日状返信 |
| 8セット | 15:七月晦日状往信 16:八月七日状返信 |
| 9セット | 17:八月十三日状単信 |
| 10セット | 18:九月十三日状往信 19:九月十三日状返信 |
| 11セット | 20:十月三日状往信 21:十月三日状返信 |
| 12セット | 22:十一月十二日状往信 23:十一月日状返信 |
| 13セット | 24:十二月三日状往信 25:十二月三日状返信 |
| (最後に) | XX:奥書 |
進捗報告や誘いの断り、自慢話など、当時の人々の息遣いがリアルに書かれています。建物の部位名や魚・植物の名前などが、めっちゃ列挙されている往来物もあります。
原文と共にお楽しみください。
| 前の記事へ << | 正月状へ >> |