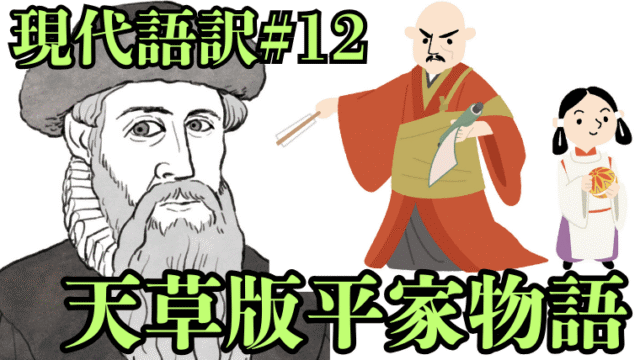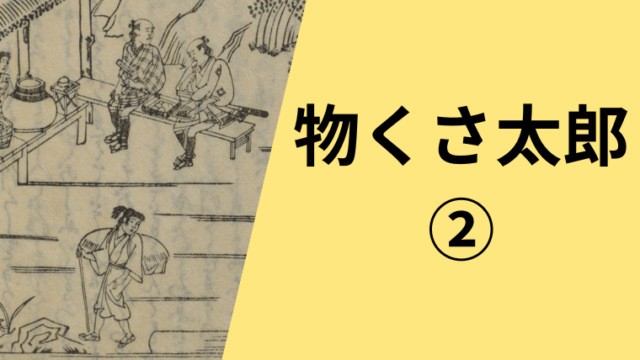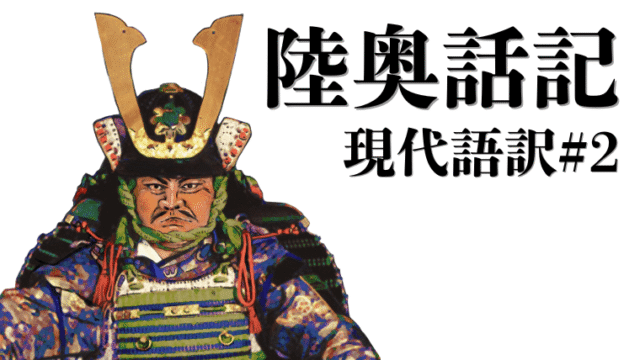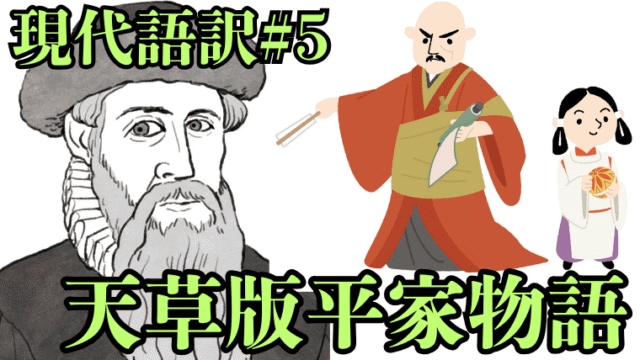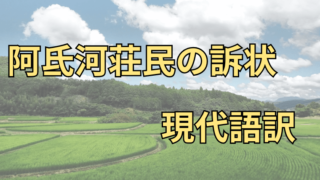交渉1
城内の食料が底つきて、籠城していた者は皆嘆き悲しんだ。武衡は義家の弟義光に使者を遣り、義家に降伏する旨を伝えさせた。義光が兄義家将軍にこれを語ると、義家将軍はあえて降伏許さなかった。その後義光のもとに参上した武衡は慎重に、言葉を選んで義光に語った。
「我が主よ。畏れ多くも申し上げます。降伏いたします故、是非城内においでください。そのお供ができれば、私の心は救われます。未練はございません。」
義家将軍は、義光が城内に向かう、という話を聞いて、義光を呼んで次のように言った。
「古今東西、大将や次将が敵に呼ばれたからといって素直に敵陣へ行くなど聞いたことがない。義光。お前がもし武衡や家衡にとりこめられるようなことがあれば、無駄だと分かっていても、私は何度でも後悔の念を感じるだろう。また、源氏は末代にまで非難され、これがきっかけで様々な事実や栄光が嘲けられかねない。城内への同行は認めん。」
義光が話に乗ってこないので、武衡が重ねて義光に言った。
「あなた様がいらっしゃらないのであれば、相応な使いを一人よこしていただきたい。その者に、我々の考えを申し上げましょう。」
義光は、自分の家来の中から、「誰か行かないか。」と人選していたところ、皆が「季方こそ適任である。」というので、季方を使いとして武衡のもとへ送った。
交渉2
季方は赤色の狩衣に、青色の紋無しの袴を履いて、太刀を携えた。籠城していた城門が初めて開いた。すぐに季方を入れると、そこは兵が垣根のように立ち並んでいた。弓矢や太刀、刀は道の両脇に並んでいた。これら武器が備えられている様はまるで林のようであった。季方は僅かに身を大きくして歩みを進めた。城を登り待機してると、武衡がやってきて非常に喜んだ。対して家衡は季方が近くにいるというのに出てこなかった。武衡は、
「折れていただけませんか。お助けいただきたい。兵衛殿(源義光)にそう申していただきたい。」
と言い、金を多く季方の前に差し出した。
「城内の財物は今日頂かなくても、落城すれば我々のものです。」
そう季方は返し、金を受け取らなかった。
武衡は大きな矢を取り出して、
「これは誰が使う矢でありましょうか。この矢が飛んでくるごとに必ず誰かが被弾する。射られた者は皆死んでしまいました。」
と語った。
季方がこれを見て言う。
「これは私が使っている矢です。」
また立ち上がって言った。
「もし私を人質にとろうと思うのならば、今ここでこの身を好きにしてください。この城から出る時、我が軍の兵が見ている中で、そこら中にいる兵に捕えられるのは、極めて決まりが悪い。人質になるくらいなら、煮るなり焼くなり好きにしていただきたい。」
武衡が返す。
「仰っているような事をするつもりはありません。ただただ早く自陣にお帰りになって、我々の考えを申し上げてほしいだけなのです。」
季方は来た時と同じように兵の中をかき分けながら城門へ進んだ。その最中、太刀の柄に手をかけて笑みを零していた。少しも変わった様子もなく自陣へ帰っていった季方。この話は世の中の人々の語りぐさとなったのであった。
寒さに堪える
城を包囲してから月日が経ち、季節が秋から冬へと移り変わった。義家将軍の兵どもは、寒く冷たいために凍え、皆悲しみの声を上げた。
『昨年は大雪が降った。あの時のように雪が降るのは今日か明日か、いつでも降りそうな様子である。これに遭遇したら凍え死ぬことは疑いようもない。我々は義家将軍の兵として奥州赴任に随行した。それゆえに妻子は国府に住んでいる。どのようにすれば、都に上る事ができるだろう。』
と言い泣く泣く文を書いた。
『我々は一丈の雪に溺れて死のうとしている。これを売って、得た金でどうにかして都へ帰り上りなさい。』と。
文に付けて、着ていた着背長(=鎧)を脱ぎ、乗っていた馬までも国府へ送ったのだった。
女子供の惨殺劇
城内では飢餓が深刻化しており、最初は下女や子供などが城の門を開いて外に出た。義家軍の兵はこれを通してやった。城内の者はこれを見て喜び、大勢が群がって門を出てきた。季武(詳細不明)が将軍に申し上げる。
「出てきた下女や子供の首をはねましょう。」と。
義家将軍、その理由を問うた。季武は返す。
「目の前で殺されるのを見れば、城内に残った者が出てくることは無くなります。これから出てくるはずだった者が城内に留まるわけですから、城内の兵糧はより早く底尽きます。既に季節は冬。兵は雪の被害を受けることを昼夜恐れておりますゆえ、早く城を落としたいと願っております。それに、今城から出ている子供や女は城内に籠る兵の愛妾や血の繋がった子供です。夫は、食料を妻子に分け与えないで自分一人で食料を食うようなことはしないでしょう。同じ頃に餓死するはずです。つまるところ、見せしめに殺して女子供が出てこないようにして、城内の食料を早く底尽かせ、季節が厳しくなる前に落城させるのです。」と。
義家将軍はこれを聞いて「尤もだ。」と言って、城から出てきた者を皆、城内の者が見ている前で殺した。これ以降、城から出てくる者は現れず、城門は固く閉ざされた。
義家の奇策
(→ここから下巻)
藤原資道は義家将軍と特に親しくしている家来である。歳はわずか十三歳。それでいて義家将軍の陣中に入ることを認められている。夜も昼も資道は義家から離れることは無かった。夜中、義家が資道を起こして言った。
「武衡、家衡の籠る金沢柵は今夜落城するだろう。凍えた敵兵がいる仮屋に火をつけて彼らの手を炙るといい。それで落城する。」と。
資道は仰せのままに承った。命令された兵どもはこれを訝しみながらも義家将軍の言いつけ通りに仮屋に火をつけ、敵兵の手を炙った。すると、なんということか。金沢柵は本当に落城したのだった。
兵どもは義家将軍を軍神かと思った。既に季節は真冬であったが、天は義家将軍を味方したのだろうか、その日は雪が降らなかった。天の思し召しに逆らう者は、決まって敗れるのである。
武衡と家衡の籠る金沢柵は食料が底尽き、寛治五年十一月十四日の夜、落城。
地獄絵図。殺戮と陵辱。
城内の家には皆火を放った。煙の中から聞こえてくる喚き声、叫び声。まさしく地獄である。人々が四方八方に逃げる様は蜘蛛の子を散らすようであった。
義家将軍の兵は逃げ惑う人々を競って残らず殺した。城から出てきたところを殺す。城内に打ち入って殺す。殺戮の手から逃れられた人は千万に一人といえよう。武衡は城にあった池に飛び込み、顔を水草の中に出して隠れていた。
兵どもは武衡の首を求めて探し回る。ついに見つかった武衡、池から引き出されては生け捕りとなった。また義家を煽った千任も同様に生け捕りとなった。
家衡はどうか。家衡は下衆の格好に変装し、少しの間逃げることが出来た。
家衡には花柑子という馬を飼っており、この馬は奥六郡でも随一の名馬であった。家衡の花柑子を愛でる様は妻子よりも深い。自分が逃げた後、花柑子が敵兵に捕らえられてしまうことを妬ましく思い、繋いでいるところを自らの手で殺したのだった。その後、述べた通り下衆の格好に変装し、逃げたのである。
城内にいた美女は兵が競って襲い、自陣に連れ去っては暴行、陵辱を働いた。男は首を切られ、鉾にさされて先に逝った。妻はこれに涙を流し、暴行、陵辱を受けたあと、夫の後を追った。
武衡の最期
義家将軍は生け捕りにした武衡を目の前に呼び出して自らの口で武衡を尋問した。
「戦況を読み、それを駆使して敵を討つという軍法は、今も昔も変わらない。先の戦い、前九年の役で清原武則は、官符による命に従い、あるいは将軍との談義によって官軍の旗を掲げた。それゆえ、先日、お前の家来の平千任が言っていた『私は名簿によって武則に従属した形で勝利した云々。』というあれは事実誤認である。誰がそのような事を教えたのかはさておき、もし、その証拠となるものを持っているのなら速やかに持ってこい。先の戦いの論功行賞において、清原武則は夷(=俘囚の長)という卑しい身分ながら、畏れ多くも鎮守府将軍の名を拝命したのだぞ。鎮守府将軍の名を穢したと言っても良い。なぜ拝命できたか分かるか。これは我が父、源頼義将軍の計らいのおかげなのだ。これは”多大な”功労賞ではないだろうか。いや、それはない、”真に”多大な功労賞である。お前たち一族は、清原武則が従軍し安倍氏を討ったこと、その武功を父頼義将軍が認めたからこそ今の地位があるのだ。それなのにお前たちは頼義将軍の恩義を忘れ、このように謀反を起こした。私は、お前たちの助けを求めたことが一度でもあったか。私が主君であるがゆえに然るべき時もそうしなかったである。平千任は私を罵倒した際、私ではなくお前を『重恩な主』と言っていたな。その心、どういうつもりか申してみよ。」
武衡は頭を地に擦り付け、顔を上げずに泣く泣く
「一日だけでいいです。どうか猶予を下さい。」と言った。
義家将軍は兼仗大宅光房に命じて武衡の首を斬らせることにした。武衡の首をいざ切ろうとした時、弟の義光が義家将軍に目を向けて
「どうか兵衛殿(武衡)をお助け下さい。」と言った。
義光は続ける。「武士の道において、降人(降伏した者)を良きように計らうのは今も昔も変わらない道理であります。今、武衡に対して良きような計らいをしていません。それでありながら、武衡一人の首を斬るのは如何なものでしょうか。」
義家は義光を強く非難した。
「降人(降伏した者)というのは、戦場を逃れ兵の手にかからない所に逃げた後、自分の罪を悔いて後に自ら首を差し出す者のこと言うのだ。つまり、前九年の役の安倍宗任らである。武衡は戦場で生け捕りにされ、情けないことに一時ではあるが命乞いをした。このような覚悟のない者は降人とは言わない。武衡は武士としての礼法を知らない、武士以下の存在なのだ。」
そう言い放ち、武衡の首を撥ねたのであった。
平千任の最期
次に義家将軍は平千任を召し出して「先日の櫓の上で言ったこと、もう一度言ってみろ。」と言った。千任は頭を垂れて何も言わない。「その舌を切れ。」と、義家将軍は命じた。源直という者がこれを承り、手で舌を引き出そうとした。
義家将軍は激怒した。「虎の口に手を入れるもは、甚だ愚かなことである。」そう言って源直を追い払った。特に力のある兵を呼び、金ばしを持って来させて千任の舌を挟もうとしたが、千任は歯を食いしばって口を開かなかった。そこで、金ばしで歯を突き破り、無理やり舌を引き出して切り落としたのであった。
平千任の舌を切った後、木の枝に吊り下げる形で縛りつけた。足元には、『重恩な主』、武衡の首がある。千任は泣く泣く足が地につかないよう曲げていたが、しばらくすると、疲れ果てて泣く泣く主君の首を踏んでしまうのであった。
家衡の最期
義家将軍はこれを見て家来どもに言う。「二年の愁眉は今日開けた。一安心である。ただ、それでもなお恨めしいのは、家衡の首を見ていないことだ。」と。
城内の屋敷はわずかな時間で焼け落ちた。戦場に落ちている人馬の死体は、麻を乱れ散らしたかのようであった。縣小次郎次任という者がいた。奥羽でも名を馳せた兵である。城内にいる者の逃げ道があるのを知って、城から遠く退いてそこを塞いだ。
戦場から逃れる者は皆次任に捕らえられた。その中には家衡が卑しい下衆の格好をして紛れていたのだが、次任が出てきたところを見つけ、その場で殺したのだった。
首並べ
次任は家衡の首を斬って義家将軍の御前に持って来ることとなった。義家将軍は大いに喜んだ。自ら紅の絹を手に取って次任に与えた。
それだけでなく、質のいい馬一頭に鞍を着けて次任に与えた。「家衡の首を持ってこい」次任は大声で叫んだ。「誰が首を持ってくるのだ。」と義家将軍は急ぎ尋ねた時、次任の家来が家衡の首を鉾に刺して持ってきた。膝まづいて「次任殿の『手作り』でございます。」と言った。
「見事だ。」陸奥国では、首を取った者自らが首化粧することを『手作り』と言うのだとか。武衡、家衡の家来の中でも、特に近しい者の四十八人分の首を将軍の前に並べたのであった。
都の評価
戦後、義家将軍は国解を都に送るにあたり、次のように書いた。
『武衡、家衡の謀反の罪は、前九年の役における安倍貞任、宗任より重いものでした。しかし、私の力をもってして、忽ちこの謀反を鎮圧いたしました。ゆえに、武衡、家衡の追討官符を早くいただきたい。その後、京に首を持参したいと考えております。』
しかしながら、京においてこの戦いは『私闘である。』と評価されているという。官符を与えれば、報酬などを要求されるだろうから、朝廷はそれを拒否したかったのだろう。そして、正式に官符の発行が無いことが決定した旨を聞いた義家将軍は、家衡、武衡の首を道端に捨てて、虚しく京に上るのであった。
(終)
| 前に戻る << | 次の記事へ >> |