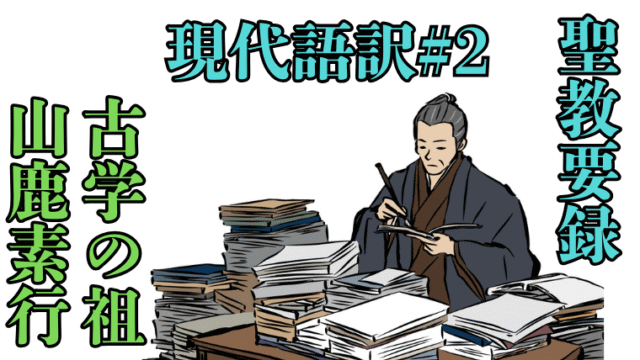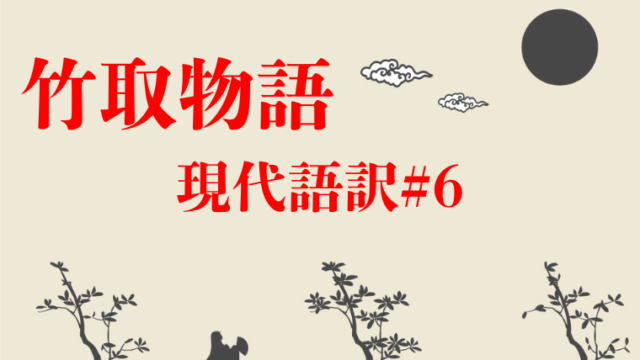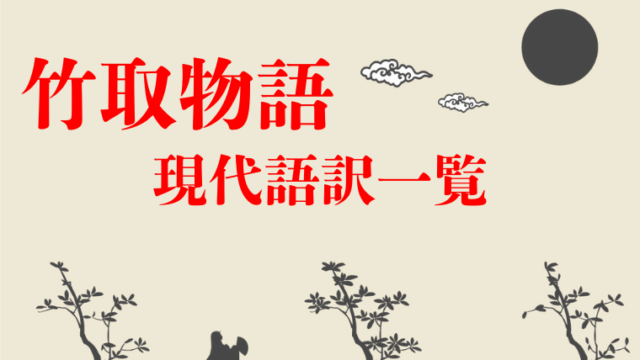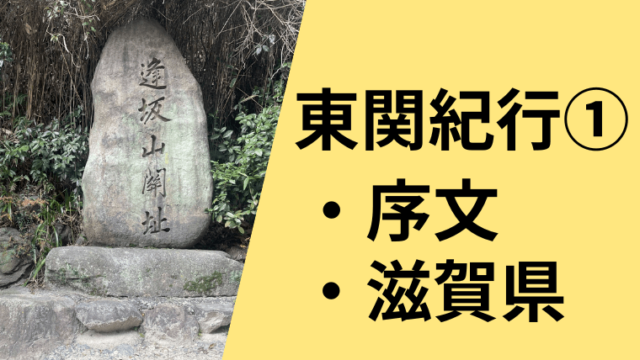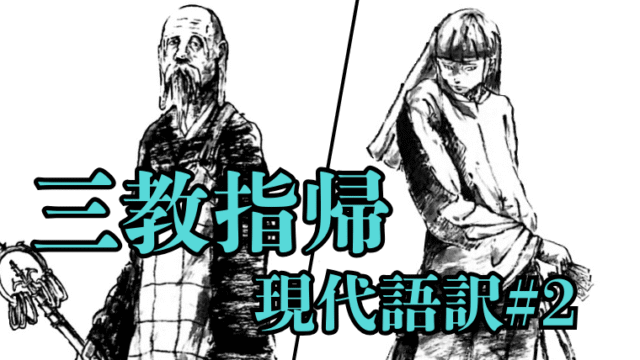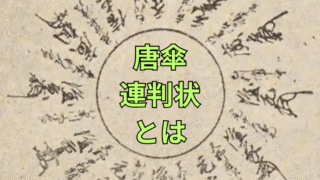田山花袋の経歴
田山花袋の蒲団は晩年の作品で、大器晩成の生涯を送りました。太文字は『蒲団』と関係の深い箇所です。岡田美知代という女性との出来事が、『蒲団』に映し出されており、様々な研究がなされています。どのような点に共通点がみられるか、このことを頭の片隅に置いて読んでみてください。
- 生誕1871年栃木県邑楽郡館林町で次男として生まれる。本名は「録弥」。父は元館林藩士田山鋿十郎(しょうじゅうろう)、母はてつ
- 15歳15歳の時に『城沼四時雑詠』という漢詩を作成し、これが初めて世に出た作品となる
- 20歳東京上野図書館に通い始め、井原西鶴や近松門左衛門やロシア文学に傾倒し「後葉会」を結成、翌年尾崎紅葉を訪問する。また、この年には柳田国男にも会っている
- 22歳初めて「花袋」の号を用い『新桜川』を連載する
- 26歳『文学界』の新年会に出席し、島崎藤村との交流が本格的に開始
- 27歳国木田独歩らと『抒情詩』を民友社から刊行する
- 33歳岡田美知代から入門希望の手紙を受け取る。なお、この年尾崎紅葉が死去。
- 34歳岡田美知代上京
- 35歳永代静雄が上京し、岡田美知代との結婚問題が起きる。
- 36歳岡田美知代は父と共に帰郷
- 37歳『少女病』を発表
- 38歳『蒲団』を発表
- 39歳『田舎教師』を発表
- ~58歳上記3作で一躍有名となり、それからは毎年3~10冊ペースで作品を発表。昭和五年(1930)、58歳でこの世を去る
優れた文才を持っておきながら、30代後半まで世間に認められなかったのは惜しい存在です。まさしく大器晩成の人物であったと言えましょう。
登場人物
登場人物は全部で7人です。
| 竹中時雄 (=渠) | 主人公。妻である細君と子どもを3人持つ。新婚生活に冷め、不満を抱く生活を送る最中に芳子に出会う。 |
|---|---|
| 横山芳子 | 神戸の女学院へ通う女学生。19歳 小説家を志し、時雄に弟子入りした。新しい時代の象徴ともいえるハイカラな性格をしている |
| 細君 | 時雄の妻。時雄の突拍子な行動も静かに受け入れるような、昔ながらの主人に従順な性格。 |
| お鶴 | 竹中家に仕える下女 |
| 姉 | 細君の姉。芳子の下宿先として一時的に世話になる。軍人の未亡人で、恩給と裁縫で生計を立てている。 |
| 田中秀夫 | 同志社大学の学生、キリスト教に心惹かれている。芳子の恋人で、芳子のことを追いかけて突然上京してきた。 |
| 芳子の父 | 芳子の父親。岡山県新見町の豪家で厳格なキリスト教徒 |
特にキーパーソンになるのは、主人公時雄と芳子、そして田中です。歪んだ三角関係を作中で広げます。
『蒲団』を読む
1:芳子との出会い
竹中時雄は34、35歳の男で、家族で暮らす単調な生活に飽きてしまい、ついには自然の風流さにまで嫌気が差すほどにまで堕落していた。こんな生活から解放されたいと、新しい恋を始めたいと切に願って日々を過ごしていた。
そんな時雄のもとに岡山の片田舎から田中芳子という女学生から手紙が届く。時雄のことを崇拝しており、将来小説家になりたいので、是非弟子入りしたいという内容であった。女性が小説家を目指すことが一般的ではなかった時代ではあったものの芳子の熱意に負け、弟子入りを認める。
文通の時期は「文字書きだから容姿にはあまり期待できない」と思っていたが、いざ対面の時、なんとその女性は、容姿端麗、才知溢れる魅力的な人物ではないか。ここから時雄の生活は明るく晴れやかなものに変化していった。
2:芳子の恋人
時雄は彼女を自分の家に居候させ、まるで新妻といるような生活を実感して非常に胸が躍っていた。しかし、そんな感情が表に出ていたせいで、妻細君の機嫌が悪くなり、加えて、親戚間の問題にまで発展していたことを時雄は知る。そこで芳子は姉のもとへ住ませることにしたのであった。僅か1か月間の夢のような生活であった。
それから1年半が経つ間に、芳子は短・長編小説や新体詩を書き徐々に作家としての才能を伸ばしていったのだが、元来ハイカラな女性なのであろう、ひたむきに机に向かうというよりも男友達と遊びに行くことが多かった。それに時雄はいい顔をできず、とはいえ強く物言えず軽く説教をする程度。関係を崩すまいとして親密な間柄を維持したまま時は流れ、ついに、事件が起きる。
田中秀夫21歳、芳子に、同志社の大学生の恋人ができたのだ!帰省から上京の途次、嵯峨に立ち寄った間の出来事であった。
3:時雄の苦悩
時雄は生活に花を添えてくれた女性を奪われ失恋したと同時に彼女の作家としての将来を不安に思った。とはいえ、保護者の立場として二人を応援しなければならない。妬み、惜しみ、悔恨など、様々な思いが渦を巻き、、、次第に酒の量も増えていった。そのことを知ってから三日間、苦しくも現実を受け入れようと上を向いたその時、この努力は無に帰す。なんと、芳子から、田中が上京してくるという旨の手紙を受け取ったのだ。男女がどのような接触をしたのか気が気でならない時雄。そして芳子を手元で管理すると決心した。手紙を受け取った日の昼から酒を飲み、ついには細君の反対を押し切ってこの事を伝えに姉の家へ向かう。
夕暮れの道中、様々な考えが頭を巡り、女性に対して久しく感じてこなかった情熱的な思いの主観、そして、最初から手は出せないことなど分かっていたという冷静な客観とが異様な心境を生み出したのだった。人生の儚さ、悲哀に時雄は涙した。
姉の家に着いた頃にはすでに夜であった。しかし、肝心の芳子は遊びに行ったらしく、不在。芳子を引き取りたいという旨を姉に話したところ、意外にも姉はあっさりと賛成してくれた。古風な考えの姉の家にハイカラな芳子は不釣合いだという理由だ。その後帰ってきた芳子にこの胸を話すと、意外に芳子の方も素直に受け入れた。どうやら姉と考えていたことが同じであったらしい。
引っ越しはすぐ、翌早朝に行われた。家に連れ帰った時雄は芳子に田中と離れるように進言し、芳子も「私達」の夢のためにはその方がいい、といった考えで時雄の考えに賛成してくれた。時雄は「私達」という複数形表現に不快に思ったが、結果として、芳子を連れ戻し、願わくば恋人と引き離すといった時雄の理想通りに事は進んだことには違いなかった。これまでの苦悩から一転、再び時雄は満足した生活が送れるようになったのであった。
4:田中の上京
それから約2か月後の11月、田中から芳子宛てに、「上京する」という旨の手紙が届く。当然時雄の目にも止まり、彼女を詰問したわけだが、田中の行動に唖然とした。まず、芳子が東京に誘ったのではなく、田中が急に始めたことだという。そしてさらに驚くのは、その手紙をよこした時点ですでに出立の支度まで済ませ、もう東京に向かう途中だったということだ。田中は東京で、文学で生計を立てるつもりのようだ、そう聞いた時雄は、常識のないこの青年に見込みがないと青ざめたのだった。
5:恋に溺れる
それから2,3日して田中が時雄の家にいる芳子を訪問しに来た。その時初対面した細君と下女のお鶴には、田中は嫌な人に見えたようで。2階の書斎で監督しても2人の接触は防げない。時雄の機嫌が悪くなっているのは芳子の目にも映っていた。
しかし、時雄の不快な感情とは裏腹に、田中と芳子の2人は、「時雄という人は「温情の保護者」だ」として良好な感情を示しているらしい。2人との認識の齟齬が時雄を苦しめた。その様子を見て芳子は時雄に気を使い、田中との接触を彼の前に見せないよう努力した。その策として見出したのが、時々学校を休んで田中の訪問するというもの。このことを知った時雄はより一層懊悩することとなる。秋が深まったころ、時雄はついに見るに堪えかねて、芳子の父に手紙を出した。「温情の保護者」として二人の逢瀬を認めてあげてほしいという内容である。様々な感情を抑えて芳子の思いをくみ取るかたちで弁明した内容を書いた。がしかし、芳子の両親はこれを猛烈に反対する。
その後、仕事の関係でしばらく家を空けることになった時雄だが、2人のことが心配で気が気でならない。細君によれば、その間にさらに恋に溺れてしまったという。芳子の家を空ける頻度が増えたり、田中と電車で一夜を明かしたりといった状況で、少々口論をしたと細君は語った。1月5日の夜、出張先の旅館に芳子から手紙が届く。
『親は考え方が古いので私たちの関係を許してくれません。ですが、親を離れて夫に従うという聖書の言葉を援用し、田中に付いていくことにしました。上野図書館で女の見習い生を募集していたので、応募してみようと思います。2人で懸命に働けば先生のもとを離れてもなんとか生活していけると思っています。お許しください。』
時雄はこの手紙を読んで激昂した。なんだ、2人のために尽力したのに、この好意を仇で返すとは義理知らず、情知らず、と。そして、無気力な生活に活力をくれた芳子を手放そう日が来ると思うと、時雄は涙を流すのであった。
時雄は自分の境遇を2人の将来に重ね、女子の憐れむべき運命を悟り、芳子の両親に宛てて手紙を書いた。以前のような「温情の保護者」の立場は、もうない。
『芳子の将来を考えると私と御父上とは意見が一致します。この問題を解決すべくぜひ上京してくだされ。』
そして時雄が出張から東京に帰った1月10日、数日後に東京に行くと芳子の父から連絡が入ったのであった。
6:父の訪問
芳子の父が時雄の家を訪問したのは6日後の16日の昼であった。芳子も田中も、芳子の父が来ることを希望しており、特別驚いた様子でもなかった。父は長旅に疲れたという御様子で、訪問、対して芳子は風邪をこじらせており病み上がりの時期であったったと同時に父に会うのが怖く部屋で泣いていた。いざ父の前に顔を出しても上手く話せず、時雄と芳子の父との会話が始まった。当然話題は2人の今後について。芳子の父は芳子が田中という男に騙されているのではないかと疑問を感じており、また、村の有力者である父は世間体的にも芳子をこのタイミングで連れ戻すのは面白くないと考えていたようであった。つまり、この考えの解決策として取るべき手段であり結論は、田中を京都に帰し、芳子を東京に置く、ということであった。
1時間ほどして田中が時雄のもとを訪れた。田中は芳子を自分のものにする権利があると言わんばかりの様子で、父と保護者に対し、服従というよりは抵抗の意思が感じ取れた。県議会の経歴を持つ芳子の父と演説に慣れた田中の応酬は真面目かつ激しいものとなった。時雄も中頃から沈黙が増えるほどに。
そして話題は田中の京都帰郷問題に発展した。田中が芳子を追って後から上京したこと、反対と言いながら恋愛を完全に反対していない芳子の父の温情があったことを根拠に、田中が劣勢に立たされた。そして父は、3年間、芳子と誠実な関係を長く維持できたら結婚も考えてやらないわけではない、と2人を案じた心のうちを話し、ついに田中は涙したのだった。なんと厚い父親なのだ。そして帰郷するか否か決断する時、別室にいた芳子が「私が帰る」と発言、それを聞いた田中は、芳子の父の温情を受けていながら「どうしても京都には帰れない」と発言する・・・。最終的に、田中に考える時間を与えることで、小一段落ついて解散となった。
田中が帰った後、父はどうも2人に不誠実な関係があるのではないかという疑問をぬぐい切れない様子であったため、時雄は芳子に対し、事の発端であった嵯峨行きの際の手紙を求め、身の潔白を証明するよう指示した。しかし、芳子は当時の手紙をすでに焼いてしまったと主張、そんなわけはないと時雄は受け入れず、その晩またしても懊悩したのだった。苦しいのは時雄だけではない、芳子も同じだ。愛し合う恋人との関係を今後どのようにしたら良いのかひとり苦悶していた。。。
7:告白と決着、そして・・・
次の日、芳子は時雄に対して一通の手紙を渡した。
『私は旧派の女です。新しい思想を行う勇気はありませんでした。先生が私のために苦悩されていると思うと、胸が痛むのです。誰にも打ち明けまいと思っていましたが、先生にだけ申し上げます。この憐れな女をお憐れみ下さい。』
時雄はこのような懺悔をこのタイミングでした理由を考える余裕がないほど衝撃を受けた。そして、芳子の帰国が至当な行いだと判断し、芳子もこれを諾したのだった。
昼飯御すぐに支度をし、時雄は父を訪れ芳子を預けた。芳子は運命の残酷さに身を委ねる事しかできず、泣きも笑いもせずにただ呆れたような様子であった。翌日朝、田中の家へ。芳子の告白と帰国の決定を伝えると、顔がわずかに変わり、様々な感情が胸を衝いてはじっとできずに家を出ていった。
その日の18時の便で帰京することが決まった。荷物は後日配達。時雄の表情は以前よりも軽快であった。芳子の美しい表情を見れないのは悲しいものの、それ以上に競争者の手から芳子を離すことができたことの方が愉快に感じたのだ。
15時、芳子、芳子の父、時雄がそれぞれ車に乗って計3台が出発した。出発してすぐの曲がり角に茶帽子の男が立っており、芳子は2,3度振り返るのであった。旅館を経由し駅に着いたのは17時ごろ。駅のその光景は旅客の悲哀、喜悦、好奇心が渦巻いているようであった。そして時間が来た。座席に就いた芳子の白い顔が浮彫のように時雄の目に移った。その時雄は、妻がいなかったら芳子をもらえたのではないか、運命は奇妙な力を持っている、もしかしたら・・・。と空想に耽っていた。そんな時雄の後ろで見送り人の群衆の中に男が一人立っていたのだが、芳子と芳子の父はそれに気づくも、時雄は気づかなかった。
そのまま、発車した。
8:蒲団
再び不愉快な感情渦巻く生活に逆戻りした時雄。これという進歩もなくただ3年前に戻っただけであった。芳子が帰国してから5日後、礼儀正しい文章で、これまでの感謝の気持ちが綴ってあった。
読み終えると時雄は芳子が住んでいた2階に上がり、
そして、捨ててあった赤いリボンを嗅ぎ、押し入れにあった蒲団と夜着を取って、それも全力で嗅ぐ。
性欲と悲哀と絶望が時雄を襲い、蒲団を敷き、夜着をかけ、冷たい汚れた天鵞絨(てんがじゅう=ビロード)の襟に顔を埋めて、泣いた。
解説へ→