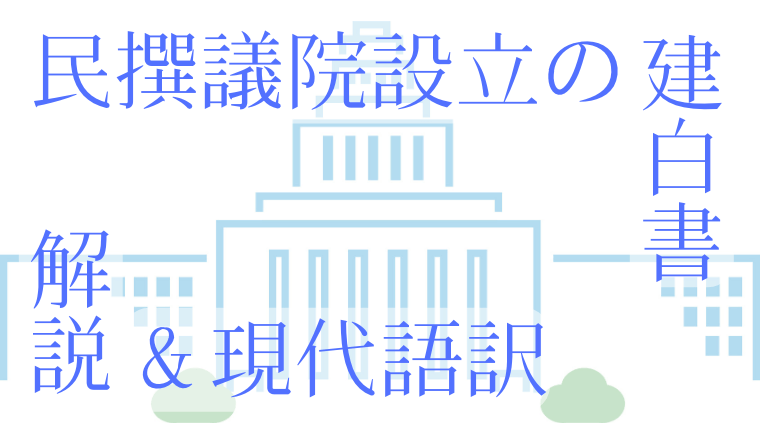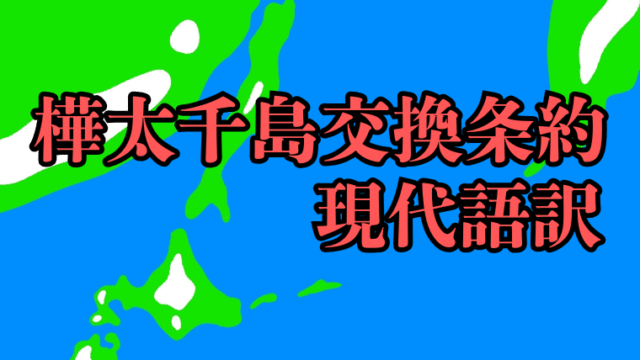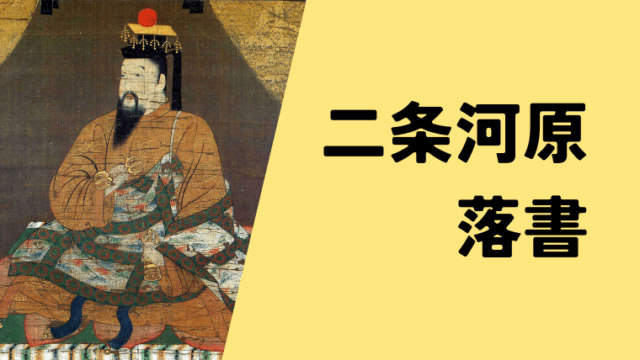プロフィール帳
解説
民撰議院設立建白書は愛国公党の党員によって出されました。板垣退助や後藤象二郎といった名の馳せた人物もメンバーになっています。「民撰議院」は、読んで字のごとく、国民(臣民)によって選ばれたメンバーによって構成された議院のことで、この建白書によって議会制民主主義の必要性の声が高まったり、自由民権運動の起爆剤になったりと、明治政治史に大きな影響を与えました。
ここでは、民撰議院設立建白書が出されるまでの経緯や内容まで全て解説していきます。
「愛国公党」結党の流れ
民撰議院設立建白書を出したのは「愛国公党」という政党で、1874年に結党されました。民撰議院設立建白書が提出されたのと同じ年です。要するに、ある出来事がきっかけで民撰議院の必要性を感じた人物らがいたということです。詳しく見ていきましょう。
明治6年(1873)、岩倉具視率いる「岩倉使節団」が欧米視察から帰国するまで、日本政府は薩長土肥による政治体制が敷かれていました。使節団が留守の間、朝鮮半島の武力開国を推奨していた征韓論者の西郷隆盛・板垣退助・後藤象二郎らが政権を主導していたのですが、本来の主導的立場であった使節団が帰国の後、政治の方針は使節団の主張である国内統治の優先が主流となり、征韓論は封じ込められてしました。これに抗議した征韓派が一斉に辞職。明治六年の政変が起こりました。
明治六年の政変についてはこちらで解説しています。
辞職した征韓論者は何をしたか。辞職した板垣退助・後藤象二郎らは、イギリス政治を学んだ古沢滋・小室信夫らと接触し、西欧の議会制議院に大きな感銘を受け、明治七年(1874)1月12日に、日本初の政党「愛国公党」を設立しました。
愛国公党に入党しなかった西郷隆盛は辞職後、地元鹿児島で私学校(軍事学校)を開き、西南戦争のきっかけを作りました。西南戦争の起爆剤にもなった神風連の乱なども近代化政策による西洋風俗の流入に危機感を覚えたことがきっかけです。
明治政府の近代化政策や明治六年の政変は、様々な衝突を生む結果となりました。
これは、西欧の議会制議院に倣った国家運営の確立を目指したもので、薩長土肥による専制政治の改革と、排除された征韓論の声を再びあげるきっかけを作ることが最初の目標となりました。
なぜ民撰議院の設立が必要だった?
当時の明治政府は、明治維新で功を立てた薩摩、長州、土佐、肥前で構成されたメンバーによって国家の運営が行われていました。要するに、国民(臣民)の意見は一切その議論や決定に反映されない運営体制が取られていたわけです。西欧議会では、一部制限はありますが、国民の選挙によってその代表者が選ばれており、国家運営に少数派の意見を発言する機会が与えられていました。
専制政治で進められた明治政府の近代化政策は何もかも順調であったわけではなく、その反動として足尾銅山鉱毒事件をはじめとする公害も発生しました。また、征韓論者が排除された事実があったように、柔軟な国家運営がとられていなかったのが現状です。
明治政府が近代化を目指したのは、欧米列強に植民地支配されないようにするための国力増強が目的で、それら国々に追いつくためには、彼らの模倣が必要でした。そう考えると、いずれにせよ民撰議院の設立が必須だったと思われますが、ただ、今この現状を推し進めるには、専制政治体制を維持した方が効率が良いのもまた事実でした。
この点に牙を剥いたのが、征韓論の排除を経験した愛国公党だったのです。
民撰議院設立建白書の内容
今の有司による専制政治を痛烈に批判、この現状が変わらないのは、世論が国家運営に反映されていないためだと判断しました。この打開策として、官民の協力体制を敷くことが国家の強靱な基盤を築くことに必須だと論じ、その手段として議院の設立を求めました。
当時の政府高官が『「人民が開明の域へ到達する」ために議院を設立することは時期尚早』としてその意見を退けていた状況があったと述べ、愛国公党はそれはむしろ議会を通じて培われるものだと主張することで反論しました。また、欧米諸国の制度を導入すれば、日本も直ちに追いつけると強調、反論に後押ししています。
そして、明治六年の政変は官民一体になる好機だと主張し、専制政治の極右弾圧ではなく、より大日本帝国を発展させるための手段として検討して欲しいと請願し、官民臣民ともに調和した良き国家を願うとして締めくくりました。
その後どうなった?
この建白書提出後、自由民権運動の原動力となり政治変革を後押ししました。
提出されたのが1月なのですが、3月以降に地方各地で政治結社が多く結成されました。例えば、4月には高知で板垣退助が立志社を設立しました。また、1875年には、愛国公党と立志社が合併し、愛国社へ発展、全国組織化が進んだのです。
ちなみに、愛国社の次は国会期成同盟です。
この自由民権運動の世論を受けて、明治政府は漸次立憲政体樹立の詔(1875)を、国会開設の勅諭(1881)などを公表、国会開設に向けて活動を展開していきました。
ただし、自由民権運動の活発化は同時に明治政府の批判や妨害活動につながるといった事案も発生したため、讒謗律や新聞紙条例(1875)、集会条例(1880)など弾圧政策も打ち立て、これに対抗しました。
自由民権運動の波乱の攻防戦を終え、ついに1890年7月1日に第一回衆議院議員総選挙が、11月29日に第一回帝国議会が開催されることとなったのです。
では、『民撰議院設立建白書』の現代語訳をどうぞ!