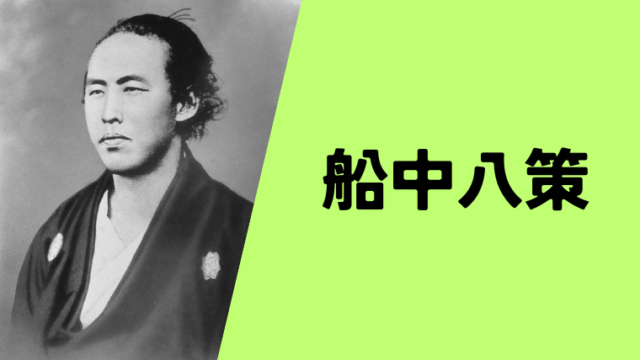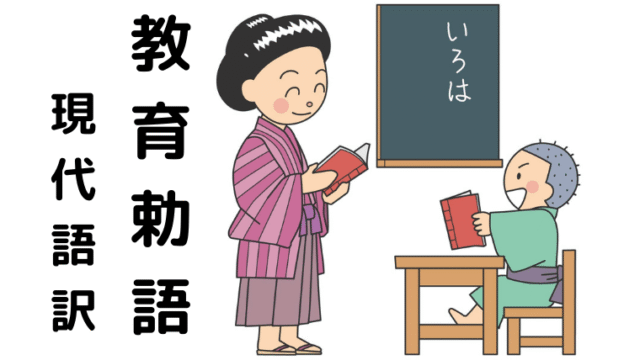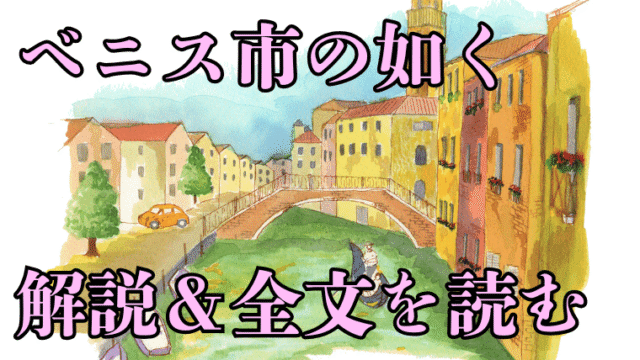プロフィール帳
解説
なぜ発令されたのか
『憲法十七条』は官吏に対して作成された心得という認識の方が多いと思います。
実際それはその通りで、「役人としてどうあるべきか」という聖徳太子の考えを仏教の考えに基づいて書かれています。
中でも、「和」「信」「義」「礼」の仏教の考えは頻出します。これらは聖徳太子が治国のために必要な精神だと考えていたのでしょう。
ちょうどこの時期から、
天皇 > 臣下 > 民
という上下構造が日本国の社会構造の前提となりました。どこかが逆転しても、全体が崩壊してもいけないわけです。仏教の考えが、これを維持するために都合のよかった考え方だったとも捉えることができます。
私は、『山陵志』において、
「聖徳太子は目新しいものを好んでいた」と評価しました。
では、聖徳太子は実際どのような心得を官吏に向けて発信したのでしょうか。以下は簡単な各条を要約です。
| 第1条 | 「和」とは尊ぶべき精神である。 |
|---|---|
| 第2条 | 三宝(仏、仏の教え、仏の教えを実践する修行僧)を敬うこと。 |
| 第3条 | 勅命は必ず謹んでお受けするように。 |
| 第4条 | 官吏は「礼」を行動の基本原理とせよ。 |
| 第5条 | 官吏は豪華さや金への欲を捨て、民の訴訟を公平に裁定せよ。 |
| 第6条 | 媚びや嘘といった悪を懲らし善を勧めよ。 |
| 第7条 | 人には各々役割というものがある。適材適所で精進せよ。 |
| 第8条 | 官吏は朝早くに出仕し、夜遅くに退出せよ。 |
| 第9条 | 「信」は「義」を実践するための根本的な部分である。 |
| 第10条 | 腹を立てるな。怒りの感情を顔に出してもいけない。 |
| 第11条 | 下の者をよく観察し、必ずそれに見合う賞罰を与えよ。 |
| 第12条 | 国司、国造は百姓から不正に税を取り立ててはならない。 |
| 第13条 | 復職した際、離職前と同様に真面目に取り組むべし。 |
| 第14条 | 官吏は他人に嫉妬してはならない。 |
| 第15条 | 自分の利益を顧みず、公のために尽くせよ。 |
| 第16条 | 民を使役する際は、農耕の閑散期など、時を選べ。 |
| 第17条 | 物事は1人で決めず、必ず議論して決めよ。 |
これを見るだけでも、現代人にも通用する教えがいくつもありますね。「第10条」「第17条」は公務員、会社員に関わらず該当するのではないでしょうか。特に人(同僚、上下関係)との関わり方に関して言及している項目が多いのが『憲法十七条』の特徴でもあります。
同時に、日本人の精神が変わっていないことが分かる史料でもあります。故に、現代人の我々にも通じるものが多いのでしょう。
聖徳太子の生涯
聖徳太子が推古天皇の補佐をしていたことは有名ですが、実は天皇家の血を継いでいたのはご存知でしょうか。そんな聖徳太子の祖父世代から自身の子世代に至るまでの伝記が存在します。それが『上宮聖徳法王帝説』です。
聖徳太子が戦争に赴いていたことや、名前の由来、その他史料の解説なども盛り込まれており、これさえ読めば聖徳太子のことが一通り分かるといった作品になっています。必読名著です。

原文
十七箇条憲法〔旧本新書体〕聖徳太子
一曰。以和為貴。无忤為宗。人皆有党。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。[JUMP]
二曰。篤敬三宝。三宝者(仏法僧也。)則四生之終帰。万国之極宗。何世誰(一作何)人。非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三宝。何以直枉。[JUMP]
三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行。万気得通。地欲覆天。則致壞耳。是以君言臣承。上行下効。故承詔必慎。不謹自敗。[JUMP]
四曰。群卿百僚。以礼為本。其治民之本。要在于(一作乎)礼。上不礼而下非斉。下无礼以必有罪。是君臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治。[JUMP]
五曰。絶饗棄欲。明弁訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尙爾。況乎累歳。湏治訟者。得利為常。見賄庁讞。便有財(一有者字)之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民。則不知所由。臣道亦於焉闕。[JUMP]
六曰。懲悪勧善。古之良典。是以无匿人善。見悪必匡。其諂詐者則為覆国家之利器。為絶人民之鋒刃。亦佞媚者。対上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆无忠於君。无仁於民。是大乱之本也。[JUMP]
七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。姦者在官。禍乱則繁。世少生知。尅(一作克)念作聖。事无大小。得人必治。時无急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社禝勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。[JUMP]
八曰。群卿百僚。早朝晏退。公事靡譼。終日難尽。是以遅朝不逮于急。早退必事不尽。[JUMP]
九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。群(一作君)臣。共無信。万事悉敗。[JUMP]
十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。誰(一作詎)能可定。相共賢愚。如環无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我独雖得。従衆同挙。[JUMP]
十一曰。明察功過。賞罰必当。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。[JUMP]
十二曰。国司国造。勿歛百姓。国靡二君。民无両主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王家臣。何敢与公。賦歛百姓。[JUMP]
十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曽識。其以非与聞。勿妨公務。[JUMP]
十四曰。群卿(一作臣)百僚。无有嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百歳之後。乃今遇賢。千載以難得一聖。其不得賢聖。何以治国。[JUMP]
十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡(一有夫字)人有私必有恨。有恨必非固。(一作同)非固(一作同)則以私妨公。恨起則違制害法。故初章云。上和下睦。(一作上下和睦)其亦是情歟。[JUMP]
十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。従春至秋。農桑之節。不可使民其不農何食。不桑何服。[JUMP]
十七曰。大事不可独断。必与衆宜論。小事是軽。不可必与衆。唯逮論大事。若疑有失。故与衆相辮。辞則得理矣。(一无矣字)[JUMP]
右十七箇条憲法以屋代弘賢蔵本及日本書紀太子伝暦拾芥抄所載挍合各有異同今従是者為定本[JUMP]
現代語訳
第1条
一曰。以和為貴。无忤為宗。人皆有党。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。
一に曰く。
「和」とは尊ぶべき精神である。この精神に逆らってはならない(受け入れよ)。しかしながら人というのは皆、同じ意思を持った者同士で徒党を組む習性があり、和を尊ぶことの正しい意味を知る者は少ない。それが原因で、君主や父といった目上の者に従わなかったり、近隣の住民と争いを起こしたりしてしまうことがある。
上の者が和やかに、下の者が懇意に議論すれば、自然と物事の道理に通じるのだ。そうなれば、何事も成すことができるだろう。
第2条
二曰。篤敬三宝。三宝者(仏法僧也。)則四生之終帰。万国之極宗。何世誰(一作何)人。非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三宝。何以直枉。
二に曰く。
三宝を敬うこと。三宝とは、仏、仏の教え、仏の教えを実践する修行僧である。この三宝は、命ある全ての生物の拠り所である。全ての国に準ずる究極法である。いつの時代、どこの誰がこの法を尊ばないことがあっただろうか。
人とは元来、極悪な性を持つ者が少ない生き物で、正しく教え導けば正道に従うという習性をもつ。その正しく教え導くために、三宝が必要なのである。この三宝の他に、何が人々の曲がった心を正すことができようか。
第3条
三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行。万気得通。地欲覆天。則致壞耳。是以君言臣承。上行下効。故承詔必慎。不謹自敗。
三に曰く。
勅命は必ず謹んでお受けするように。君主を天とするならば、臣下は地である。天は地を覆い、地は天の恩恵に授かる。これが道理である。
季節はこの道理に従って巡り、万物は季節ごとに異なる気を受けて成長する。もし、地が天を覆うようなことがあれば、この道理が壊れてしまうだろう。
道理を保つために、臣下は、君主がものを言えば謹んで承って実行する必要がある。上の者が君主の命令に従えば、下の者も自然にそれに従うのである。それ故、臣下たる者、勅命があれば承り、必ず奉じよ。謹んで奉じなければ、先に記した道理は自ずと崩壊するだろう。
第4条
四曰。群卿百僚。以礼為本。其治民之本。要在于(一作乎)礼。上不礼而下非斉。下无礼以必有罪。是君臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治。
四に曰く。
官吏は「礼」を行動の基本原理とせよ。「礼」とは、仁愛の心を行動で示したものである。もっとも、民を治めるための基本的なことは必ず「礼」にある。上の者に「礼」が備わっていないと、下の者が乱れ、秩序が保たれない。逆に、下の者に「礼」が備わっていないと、必ず犯罪が起きてしまう。
つまり、諸官吏が「礼」を備えれば、身分の上下が乱れず、国の秩序が保たれるのである。また、民衆が「礼」を備えれば、国家は自ずと治まるのである。
第5条
五曰。絶饗棄欲。明弁訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尙爾。況乎累歳。湏治訟者。得利為常。見賄庁讞。便有財(一有者字)之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民。則不知所由。臣道亦於焉闕。
五に曰く。
官吏は豪華な食事を辞め、金品への欲を捨て、民の訴訟を公平に裁定せよ。民の訴えというのは、1日に1000件あると言われるほど多く存在する。1日ですらこの量である。ああ、歳月を重ねればいったいどれほどの量になろうか。
近年、訴訟に従事する者は常に私利私欲のために動いており、賄賂を受け取っては、渡した者の言い分によく耳を傾ける。裕福な者の訴えは石を水に投げ込むがごとく簡単に聞き入れられ、貧しい者の訴えは受け入れられないのである。掴んだ水を全て石に投げつけるのが難しいように。。。そのため、貧しい民は何を頼るべきか分からないでいるのだ。このような状態は、臣下としての道理を欠いていると言える。
第6条
六曰。懲悪勧善。古之良典。是以无匿人善。見悪必匡。其諂詐者則為覆国家之利器。為絶人民之鋒刃。亦佞媚者。対上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆无忠於君。无仁於民。是大乱之本也。
六に曰く。
悪を懲らし善を勧める者は、古から続く人としての良い模範である。そのため、他人の善行は隠さず公にし、悪行は見過ごさず、必ず正すように指摘するべし。
媚びたり、嘘をついたりすることは国家を傾けるのに効果的な武器であり、同時に人民を傷つける鋭利な鋒(ほこさき)でもある。また、媚びへつらう者は、「上の者に対しては好んで下の者の失敗を報告し、下の者に対しては上の者の失敗を非難する」といったことをする。このような人らは皆、君主に対する忠義心はなく、人民に対する仁徳もない。そして、国家が大きく乱れる根本的な原因となる。
第7条
七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。姦者在官。禍乱則繁。世少生知。尅(一作克)念作聖。事无大小。得人必治。時无急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社禝勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。
七に曰く。
人には各々役割というものがある。特に官吏に関しては、その職権を濫用してはならない。賢くて、才知が優れている者がその職に任ぜられると、褒めたたえる声があがる。しかし、邪な人がその職に在任していると、頻繁に災いや乱れが起きる。生まれながらにして道理を知る者は少ない。ほとんどが、道理を学びながら聖人となるのである。
事の大小に関わらず、職と能力が適合すれば、災いや乱れなく、必ず治めることができる。時代によって世の乱れの程度が大きく変動したことはない。それは、賢人が治国に携わってきたことで、自ずと国家が安定していたからである。このために、国家は傾くことなく、永久に在り続けることができるのである。
故に、古の聖王は、必要な官職のために人を求めることはあっても、人のために治国に不要な官職を設けることをしなかったのである。
第8条
八曰。群卿百僚。早朝晏退。公事靡譼。終日難尽。是以遅朝不逮于急。早退必事不尽。
八に曰く。
官吏は朝早くに出仕し、夜遅くに退出せよ。公的機関の仕事が終わることなどない。1日かけても終わらせることが難しい量あるのだ。そのため、朝遅くに出仕すると不測の事態に対処できなくなるし、早く退出すると仕事が間に合わなくなる。
第9条
九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。群(一作君)臣。共無信。万事悉敗。
九に曰く。
「信」は「義」を実践するための根本的な部分である。「信」は信頼のこと、「義」は人としての正しい行いのことである。そのため、何事に取り組む(=「義」)にしても「信」は必要なものである。善悪や成功失敗といった違いには、必ず「信」の有無が影響している。
臣下が共に「信」を備えていれば、何事(=「義」)も成すことが出来るだろう。逆に、「信」を備えていなければ、何事も成すことは出来ないだろう。
第10条
十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。誰(一作詎)能可定。相共賢愚。如環无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我独雖得。従衆同挙。
十に曰く。
心の中で腹を立てるな。その感情を顔に出してもいけない。他人と意見が違っても怒ってはいけない。人には皆それぞれ心があり、それぞれ異なる考え方を持っているからだ。
相手が良いと思うことは自分にとって悪いことがある。逆に、自分が良いと思うことは相手にとって悪いことがある。自分は必ずしも聖人とはいえないし、かといって相手も必ずしも愚人とはいえない。互いに平凡な人なのだ。良い悪いの基準というのを、平凡な人がどうして決めることができようか。自分も相手も互いに賢く、そして互いに愚かである。これは金属の輪に端がないようなものである。
そのため、相手が自分に怒っている時は、自分の過ちを反省しなさい。自分一人の意見が道理に叶っていると思っても、皆の意見を尊重し、聞き入れるべきである。
第11条
十一曰。明察功過。賞罰必当。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。
十一に曰く。
下の者の功績と過失をよく観察し、必ずそれに見合う賞与と罰を与えるべきである。近年、賞与の基準に功績をみておらず、罪の基準に過失をみていない。特に、賞罰を司る職の官吏はその判断を適正に行うべきである。
第12条
十二曰。国司国造。勿歛百姓。国靡二君。民无両主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王家臣。何敢与公。賦歛百姓。
十二に曰く。
国司、国造は百姓から不正に税を取り立ててはならない。一国に君主は二人いてはならないし、民にとって主は二人いてはならない。この国に住む民にとって王とは天皇のことである。そのため、任ぜられる官吏は皆天皇の臣下なのである。官吏は民にとっての王ではない。どうして法で公的に決められた税と別に私的に税を取り立てることができようか。
第13条
十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曽識。其以非与聞。勿妨公務。
十三に曰く。
諸々の官職に任ぜられた者は互いの職について知るべし。人によっては、病にかかったり、使いとして派遣されたりして、実務から離れ、本来の仕事ができなくなることがあるだろう。
しかし、本来の職に戻った時は、一時離職していたとはいえ、昔からその仕事について熟知しているかのように、真剣に働くべきである。
「職から離れていたため、これは今の自分がやる仕事では無い」と言って当事者意識を持たず、公務を妨げてはならない。
第14条
十四曰。群卿(一作臣)百僚。无有嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百歳之後。乃今遇賢。千載以難得一聖。其不得賢聖。何以治国。
十四に曰く。
官吏は他人に嫉妬してはならない。自分が人に嫉妬すると、人もまた自分に嫉妬するのだ。嫉妬とは際限を知らないものである。
自分より智恵が勝る者をみると不快に思ってしまい、自分より才能が優れた者をみると嫉妬してしまう。そのため、「500年に1度現れる」という賢人に出会ったとしても、嫉妬して周りが賢人を受け入れないだろう。これでは、「1000年に1度現れる」という聖人を受け入れることは更に難しい。そのような賢人、聖人を受け入れられないで、どうして国を治めることができようか。
第15条
十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡(一有夫字)人有私必有恨。有恨必非固。(一作同)非固(一作同)則以私妨公。恨起則違制害法。故初章云。上和下睦。(一作上下和睦)其亦是情歟。
十五に曰く。
自分の利益を顧みず、公のために尽くすことは臣下としてあるべき姿である。
一般に、利己心が芽生えている時は必ず他人に恨みを持っている。他人に恨みがあると必ず人の和が乱れてしまう。和を乱すということは、和が尊ばれる公務を妨害することを意味する。それは自分の利己心が原因なのだ。また、恨みから法を犯す者もいるほどである。
だから、第一条でも記した通り、上の者も下の者も仲睦まじく関わり合う必要があるのだ。この条で記したことも第一条の趣旨による。
第16条
十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。従春至秋。農桑之節。不可使民其不農何食。不桑何服。
十六に曰く。
時を選んで民を使役することは、古から続く人としての良い模範である。冬は農業を終えて閑散としている期間である。そのため、冬に民を使役するべきである。
春から秋に至るまでは稲作、養蚕の時期であるため、民を使役してはならない。農耕しなければ食べるものが無くなってしまい、養蚕しなければ、着るものが無くなってしまう。
第17条
十七曰。大事不可独断。必与衆宜論。小事是軽。不可必与衆。唯逮論大事。若疑有失。故与衆相辮。辞則得理矣。(一无矣字)
十七に曰く。
物事は1人で決めてはならない。必ず他の人と議論をして決めるべし。
小さな物事に関しては、重要性が高くないため、必ずしも他人と議論する必要はない。ただ、重大な事を議論する時は、決定に過ちが発生しないか常に疑いながら議論すべきである。そうして、他人と議論して下した判断は、道理に叶った結論となっているだろう。
出典
右十七箇条憲法以屋代弘賢蔵本及日本書紀太子伝暦拾芥抄所載挍合各有異同今従是者為定本
右の『十七条憲法』は、江戸時代の国学者である屋代弘賢の蔵書、及び『日本書紀』『太子伝暦』『拾芥抄』記載分を照らし合わた。各々異同がみられたため、これを製作するにあたってその異同を修正した。後世における標準本とする。
まとめ
『憲法十七条』が千年以上未来の我々に通ずるのは、やはり仏教の道理が変わらず受け継がれてきたからでしょう。国民性の根幹を担う要素の一つに宗教があり、これは一長一短で作られるものではありません。長い仏教史が積み重なって今の日本人を形成しているといっても過言ではありません。そしてそんな仏教史の中でも、本格的に政治に取入れ始めたのは聖徳太子が最初になります。
彼の時代の説諭が現代にも通ずるということは、この国に仏教が伝来してからずっと一貫して日本民族の精神が培われてきた、その証明ともいえるのではないでしょうか。私はそう思います。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |